ホンマでっか!?TV「顔でわかる性格診断SP」
人の顔には、その人の性格や行動の傾向、さらには健康状態まで映し出されているといわれます。今回の番組では、1億人以上の顔データ分析や相貌心理学の知見をもとに、顔の形やパーツからわかる特徴を紹介。おでこの広さや鼻の形、耳の見え方など、普段意識しない部分にも性格のヒントが隠されていることが明らかになりました。さらに、最新のAI顔解析技術が面接や営業の表情トレーニングに活用される事例や、日本人の顔の変化と食生活の関係についても解説。芸能人や有名人のエピソードも交え、顔から読み取れる情報の奥深さに迫ります。
顔の形から性格や行動傾向がわかる?
佐藤ブゾン貴子氏は、人の顔を上・中・下の3つのゾーンに分けて観察し、それぞれの特徴から行動や考え方の傾向を読み解く相貌心理学の手法を紹介しました。顔のバランスやパーツの形は、その人の性格や価値観を反映しており、日常のふるまいや意思決定にもつながるといいます。特におでこが広い人は、物事を筋道立てて考える理屈っぽい傾向が強いとされ、番組内では北山宏光、森香澄、島崎和歌子がこのタイプに該当しました。
一方で、顔の特徴から感情の優先度も読み取れるとし、感情を優先する感情優先型にはEXITや小杉竜一が分類されました。直感や欲求を重視する本能優先型には山崎弘也(ザキヤマ)や葉加瀬太郎があてはまります。また、感情と理性の間で揺れ動きやすいタイプも存在し、その代表例として吉田敬や寺島進が挙げられました。このタイプは判断に迷いやすく、結果としてストレスを抱えやすい傾向があるといいます。
さらに佐藤氏は、おでこの形から思考のスピードや想像力の豊かさまで推測できると解説しました。例えば、森香澄はじっくり考える熟考型であり、額が大きいことから創造的な発想が豊かだとされています。加えて、正面から見た顔は周囲の目を意識して整えられた「社会的な顔」であるのに対し、横顔には本人の本来の性格や無意識の表情が表れやすいと指摘しました。
これに関連して中野信子氏は、人は社会的な評価や周囲からの印象に合わせて振る舞いを変える傾向があり、それが日常の行動や表情にも影響を与えると説明しました。このため、表向きの印象と実際の内面が異なる場合も多く、相貌心理学はそのギャップを見抜く手がかりになるといいます。
左右対称の顔はなぜ美しいと感じるのか
中野信子氏によると、左右対称の顔は見る人にとって受け取る情報が少なく、脳が処理する負担である認知負荷が低くなるため、多くの人が自然と「美しい」と感じやすいといいます。つまり、顔の左右のバランスが取れていると、見る側が無意識のうちに心地よさを覚えるというわけです。
さらに梶本修身氏は、プリンストン大学で行われた研究を紹介しました。その研究では、人は相手の顔を見た瞬間、わずか0.1秒という短い時間で「この人は有能そうかどうか」を判断してしまうことが明らかになっています。第一印象は驚くほど早く形成され、その後の評価や接し方に大きく影響する可能性があるといいます。
加えて梶本氏は、顔の幅が広い人は周囲から横柄な印象を持たれやすい傾向があると指摘しました。これは性格や行動の実際とは必ずしも一致しないものの、見た目だけでそう感じられることが多く、本人にとっては誤解を招く場合もあります。なお梶本氏自身もこの特徴に当てはまると、笑いを交えて語っていました。
有名人のエピソード
寺島進は、過去にヴェネツィア国際映画祭へ参加した際の珍しい体験を明かしました。現地の入国審査で何らかの理由により足止めされ、そのままパトカーに乗せられるというハプニングに見舞われたといいます。この意外なエピソードに、会場や共演者からも驚きの声が上がりました。
さらに、小杉竜一の思い出話も紹介されました。彼は番組で共演した落合博満から、食事の席でふいに「かわいい顔してんな」と声をかけられたことがあるそうです。普段の小杉の印象とは少し異なる褒め言葉に、場が和む一幕となりました。
鼻や耳からわかる本音や協調性
佐藤ブゾン貴子氏は、顔の中でも鼻や耳の特徴から、その人の性格や行動傾向がわかると解説しました。まず鼻の穴について、正面からほとんど見えない人は秘密主義で、自分の考えや情報をあまり外に出さないタイプとされます。一方、正面から鼻の穴がよく見える人は秘密が苦手で、思ったことや感じたことを比較的オープンに話す傾向があるといいます。さらに、ニンニク鼻の持ち主は独占欲が強い傾向があり、人や物事を自分のものにしたいという意識が強めだそうです。
耳の見え方についても興味深い分析がありました。正面から耳がはっきり見える人は独立心が強いタイプで、自分の判断や行動に自信を持ちやすいとされます。逆に、正面から耳が見えない人は協調性が高く、周囲との調和を大切にする傾向があります。そして、これまで耳が見えていなかった人の耳が見えるようになってきた場合、それは独立心が芽生えてきたサインであり、起業や独立など新しい挑戦に向くタイミングだと説明しました。
AIによる顔解析の応用
永田毅教授は、2000年代のアイドルたちの平均顔写真を素材にして、北山宏光の好みや選択傾向を反映させた理想のアイドル顔を生成AIで作成しました。AIが生み出したその顔を見た北山は、「グループのセンターにいそう」と感想を述べ、完成度の高さに驚いた様子でした。
続いて牛窪恵氏が紹介したのは、表情筋の動きから感情を読み取るAIシステム「心sensor for Training」です。このシステムでは、面接や営業など状況に応じて最適な表情を身につけるための表情トレーニングが可能です。笑顔や謝罪時などシーン別の練習に対応し、AIが採点や改善点をフィードバックしてくれます。さらに、就職やアルバイトの面接練習に特化した「カチメン!」も紹介され、AIによる表情解析がビジネスや就職活動のサポートに広がっていることが示されました。
日本人の顔の変化と食生活
馬場悠男氏は、日本人の顔の形の変化について、人類学的な視点から解説しました。近年は料理技術の進化や食材加工の発達により、日常的に柔らかい食事を取る機会が増えています。その結果、食べ物を強く噛む必要が減り、顎の筋肉が十分に発達しなくなっているといいます。この傾向が長く続くことで、現代の日本人の顔は以前に比べて細長い形になってきているそうです。
馬場氏は、こうした顔の変化が見た目だけでなく健康面にも影響を及ぼす可能性を指摘しました。特に、顎まわりの筋肉や気道の構造が弱くなることで、睡眠時無呼吸症候群を発症するリスクが高まる恐れがあると警鐘を鳴らしています。そのため、子どものうちから意識的に硬い食べ物を食べる習慣を身につけ、噛む力と顎の発達を促すことが大切だと強調しました。
白目と人間だけの視線コミュニケーション
馬場悠男氏は、人間の白目の構造について解説しました。人間の目は白目と黒目の境界がはっきりしており、これによって視線の方向が他者に明確に伝わるようになっています。この特徴は、動物の中でも珍しく、相手の視線を読み取ることで意思疎通がしやすくなり、スムーズなコミュニケーションにつながっているといいます。
一方で、話題はイルカの目つきにも及びました。明石家さんまは、イルカと目を合わせたときにどこか恐怖を感じたと語り、その鋭い視線に圧迫感を覚えたことを明かしました。これに対し中野信子氏も、イルカは一般的なイメージに反して高い凶暴性を持つことを認めています。
さらに小杉竜一は、過去に番組のロケでイルカと一緒に泳がされた経験を振り返りました。そのときの緊張感や独特の距離感を思い出しながら、スタジオを笑わせる一幕となりました。
この番組では、相貌心理学からAI解析、食生活と顔の変化まで幅広く取り上げられました。顔は単なる見た目以上に、その人の性格、行動傾向、健康、そして社会での評価にまで影響を与えることがよくわかります。日常の中でも、自分や他人の顔の特徴を意識すると、新たな発見や理解が生まれるかもしれません。
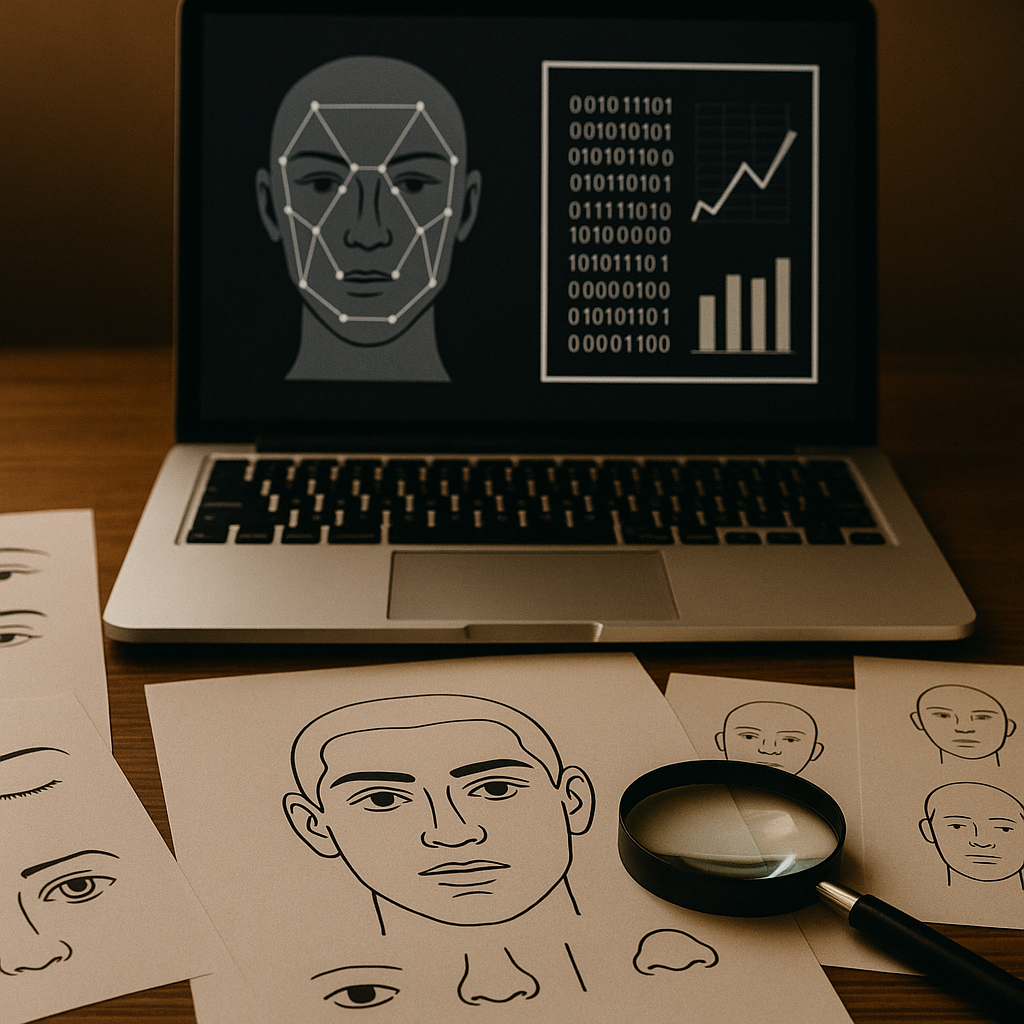
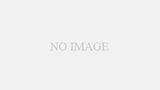
コメント