かつての“借金地獄物語”が教えてくれること
誰もが「お金がすべてじゃない」と言いながら、日々の生活はお金に縛られています。借金をした人、取り立てる人、そして競売で家を失う人。1997年に放送されたザ・ノンフィクション『借金地獄物語』は、そんな“お金の裏側”を赤裸々に映し出しました。
それから28年。2025年10月、番組は放送30周年特別企画として、あの衝撃作の「その後」を描きました。この記事では、当時の社会背景と登場人物たちの現在、そして今の日本が同じ過ちを繰り返さないために何を学べるのかを紐解きます。
1997年、“お金”が人を狂わせた時代
バブル経済が崩壊して数年。日本社会は景気回復を待ちながらも、実際には失業や倒産、ローン破綻が相次ぎました。街中には消費者金融の看板が並び、「ご利用は計画的に」というキャッチコピーが流行語になるほど。
そんな時代に放送された『借金地獄物語』は、消費社会の裏で静かに進行していた“破産連鎖”を赤裸々に映しました。
舞台となったのは千葉県市川市、浦安市、習志野市、船橋市。郊外の住宅地に次々と貼られる「競売物件」の告知。人々が夢見たマイホームが、借金によって手放されていく現実がありました。
登場人物の一人、上打田内英樹はその「競売の現場」で生きる男でした。東北の貧しい農家の次男として育ち、昭和45年に集団就職で上京。若くして警視庁の巡査になりますが、わずか1年で退職。警察を離れた後、独学で不動産の世界に足を踏み入れます。
彼の仕事は「競売屋」と呼ばれるもの。千葉地方裁判所の入札を渡り歩き、安く落札した家をリフォームして貸す。ときには裁判所を通じて強制執行に立ち会うこともありました。
相場70万円の土地を50万円で手に入れ、古びた家を取り壊して新しく建て替える。上打田内の手際は職人のように冷静で、非情にも見えるほど効率的でした。だが、その裏には「自分も貧しさから這い上がりたい」という切実な思いがありました。
“借金地獄”の中で生きる若い女性たち
もう一つの舞台は、神奈川県曙町。夜の街のネオンが光る裏通りに、小さなファッショヘルスが並んでいました。
そこで働く若い女性の多くは、借金を返すためにこの世界に足を踏み入れていました。朝から夜まで働きづめの毎日。それでも借金の額はなかなか減りません。
番組で特に印象的だったのが、元看護師の榊という22歳の女性。
彼女は500万円の借金を抱え、昼夜逆転の生活を続けていました。朝5時からの早番、そして夜12時までの遅番を掛け持ちし、1日10人以上の客を相手にすることもありました。
「お金がないと不安なんです。借金を返したら、次は自分のために1000万円貯めたいんです」
榊のこの言葉には、ただの金銭欲ではなく、「借金で傷ついた自分を立て直したい」という切なる願いが込められていました。
歩合制の仕事で、月の収入は110万円を超えることもありましたが、心の疲れは隠せません。夜の街の光の中で、榊はいつも笑顔で客を迎えながら、内側では「自由」を求めていました。
あれから28年──成功者となった“競売屋”の今
番組の後半では、28年後の上打田内英樹が登場しました。
今や鎌倉に自社ビルを構え、広々とした社長室に座る姿は、かつての“競売屋”のイメージとはまるで別人。扱う金額は億単位に膨れ上がり、事業規模も全国レベルへ。息子も跡を継ぎ、経営の一翼を担っています。
だが、上打田内の言葉にはかつての冷酷さはありませんでした。
「今は、人を救って利益を得る時代だと思う」
その一言には、長年“金のために働く人間”を見続けてきた男の、人生観の変化がにじんでいました。
借金で家を失った人、家族を壊した人、取り立てに疲れた人。多くの“悲劇”を見てきたからこそ、彼は「お金は手段であり、目的ではない」と言い切るようになったのです。
彼のオフィスの壁には、かつて落札した物件の写真がいくつも飾られていました。そこには「過去を忘れない」という意思が込められているようでした。
番組が描いた“お金と人間の距離”
『借金地獄物語』の再取材が伝えたのは、単なる“過去の記録”ではありません。
お金に振り回される人間の姿は、時代を超えて繰り返されています。1997年のローン破産予備軍は全国で100万世帯と予測されていましたが、2025年の今もその構図は変わっていません。
SNSや副業ブームの裏で、借金を抱える若者、奨学金を返せずに苦しむ世代、住宅ローンに縛られる家庭——現代の“借金地獄”は形を変えて続いているのです。
番組は静かに問いかけます。
「あなたはお金に使われていませんか?」
お金そのものが悪いのではなく、それをどう扱うか。どう生きるか。その選択こそが人生を決めるのです。
まとめ:お金に支配されずに生きるために
この記事のポイントは次の3つです。
・『借金地獄物語』は1997年に放送され、歴代最高視聴率15.9%を記録した社会派ドキュメントである。
・主人公の上打田内英樹は、競売屋から不動産の成功者へと成長し、「人を救うビジネス」を掲げるようになった。
・借金に苦しむ人々の姿は、今の日本にも続く“現代の写し鏡”である。
お金は、使い方次第で人を救うことも、壊すこともできます。
榊のように借金から立ち直ろうとする若者、上打田内のように利益の意味を変えた経営者——彼らの姿は、金銭よりも「生きる力」を語っていました。
30周年を迎えたザ・ノンフィクションがこの回を選んだのは、きっと“人間が変わる力”を信じているからでしょう。
お金はあなたを幸せにもし、縛りもしない。
本当の意味で自由になるには、「お金よりも、自分の生き方を選ぶこと」が大切なのだと、この回は教えてくれます。
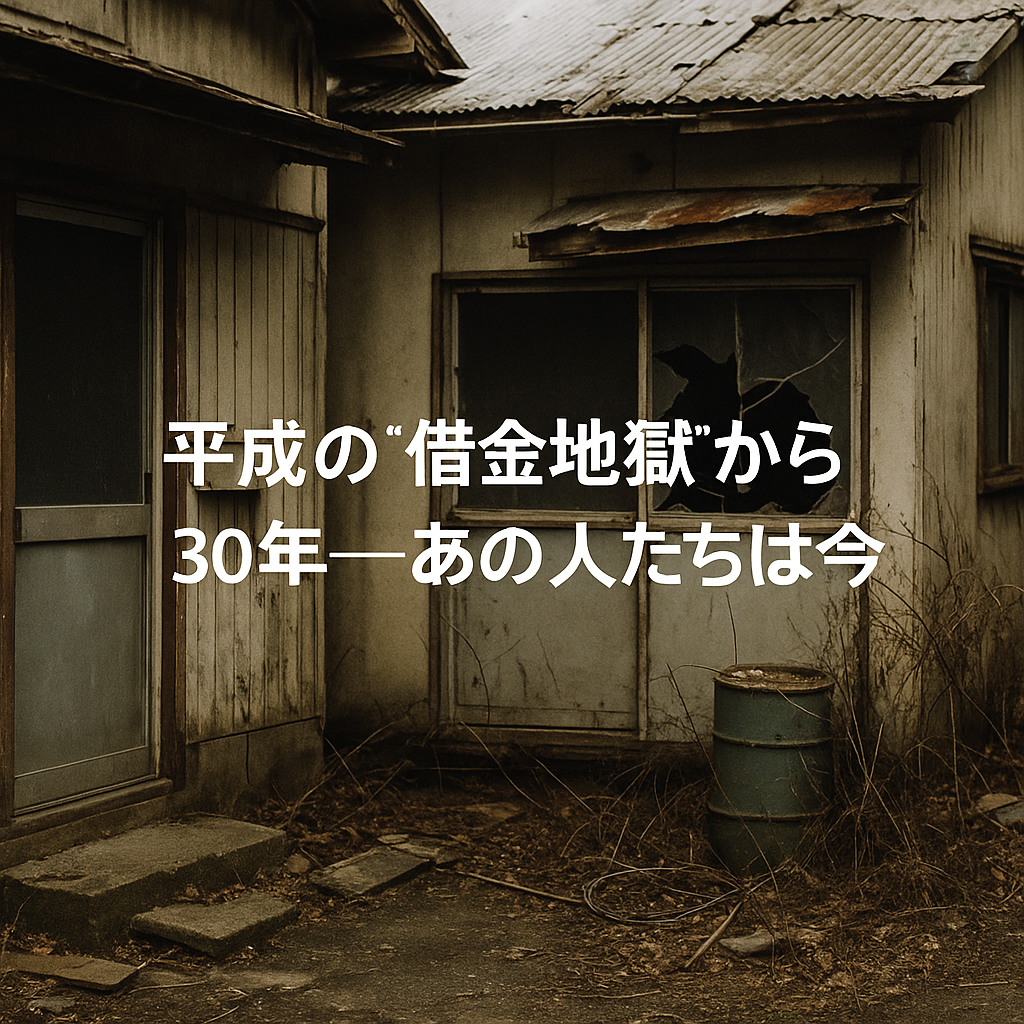
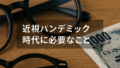

コメント