名古屋港で60年!81歳昭子さんの奮闘に密着
2025年4月13日放送の『運搬千鳥 それ、どうやって運ぶんじゃ?』(フジテレビ・16:05~17:20)では、日本有数の国際港・名古屋港で、60年もの間外国船に食料品を届け続けている女性・昭子さんの姿に密着しました。輸入の99%以上を船が担う日本にとって、港の現場で働く人々の存在は欠かせません。その中でも、船に物資を届ける「船商」の仕事は、多くの人に知られていないけれど、とても大切な役割です。今回は、昭子さんが働く「とね商店」での一日を、芸人の川村エミコさんが体験。港の裏側と、昭子さんの長年にわたる努力が紹介されました。
食料品を運ぶ“船商”とは?知られざる港の裏方仕事
番組ではまず、「船商(ふなあきんど)」という存在が紹介されました。これは、外国船が入港中に必要とする食料や生活用品を届ける専門職です。貨物船に乗る外国人船員は、1ヶ月以上もの間、船上で生活することも珍しくなく、陸に滞在できる時間は非常に限られています。その短い時間で買い物を済ませるのは困難なため、船商のサポートが不可欠なのです。
とね商店は、名古屋市内にある創業100年の老舗で、こうした外国船への納品を長年続けてきました。その中心で働いているのが、81歳の昭子さん。昭子さんは22歳の時、とね商店の2代目である一成さんと結婚し、以来60年にわたって現場の第一線で活躍しています。かつて高度経済成長の時代には、名古屋港の貨物取扱量も急増し、とね商店の業務はますます忙しくなりました。
船はいつ来るか分からない!?臨機応変が命の現場
この日、川村さんがお手伝いすることになったのは、翌日に四日市港に入港予定の、20人乗りの石油タンカーへの納品作業。天候や海の状況によって到着時刻が大きく変動するため、準備にも緊張感が走ります。
・前日に注文が入るのはよくあること
・保存のきく食材や調味料などは常時ストック
・不足分はその都度業務用スーパーなどで買い足す
この日も、注文された生のインゲンが市場に見当たらず、代わりに冷凍インゲンを用意するという判断がありました。どんな時でも「代替案を考え、すぐに動く」。それが、昭子さんの持ち味です。
また、個人ごとの注文が多いため、すべてを仕分けして袋に詰め直す作業も重要です。一人ひとりの食生活に合わせて届けるためには、効率よりも正確さと配慮が求められます。
陸から海へ。複雑な運搬ルート
四日市港に到着する船は、岸壁ではなく“沖”に停泊するため、納品にも工夫が必要です。荷物はまずトラックで港まで運び、そこから小さな船に積み替え、沖合に停泊する本船まで届けるという手順を踏みます。
・20人分の食料を1便で運ぶこともある
・天候が悪ければ、出港の可否判断も迫られる
・安全に運ぶために、しっかりと固定しながらの作業
81歳でこの一連の作業に関わっている昭子さんの姿は、まさに尊敬に値します。無理をしている様子は見せず、すべてを「いつも通り」にこなす姿には、多くの人が心を打たれたはずです。
ハプニングにも冷静対応!プロジェクターの行方
この日、もうひとつの難題がありました。船員から注文されていた特定の型番のプロジェクターが郵送で届く予定だったのですが、当日の朝になっても届かないという事態が発生。昭子さんはすぐに郵便局へ向かいましたが、その時点では未着。
結局、数日後にプロジェクターが届き、無事に依頼された品目がすべてそろいました。こうした機材の注文も受けるのが「とね商店」の特徴で、食料品に限らず、生活に必要なあらゆる物を用意することが求められています。
船員との交流と手紙の代読
番組の最後には、6日後に名古屋港に入港した韓国の自動車運搬船に対しての納品時の様子が紹介されました。そこでは、これまで支えてきたとね商店や昭子さんに向けて、船員たちが書いた感謝の手紙が寄せられており、川村さんがその手紙を代読。
・温かい言葉に、昭子さんの長年の努力が報われる瞬間
・国籍を超えた交流が、日々の業務を支えるモチベーションに
・言葉は通じなくても、心は伝わるという証し
この場面では、視聴者にとっても「支える」ということの意味を改めて感じる場面になったことでしょう。
60年にわたり、変わらず港に立ち続けてきた昭子さん。配送という単純作業のように見える仕事の中に、たくさんの人の想いとつながり、努力と工夫、責任と誇りが詰まっていました。今もなお現役で動き続けるその姿は、名古屋港の象徴とも言える存在です。
港で働く多くの人々の支えがあるからこそ、私たちの暮らしが成り立っています。そんな当たり前の背景を、あらためて知ることができる貴重な放送でした。
※放送の内容と異なる場合があります。

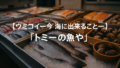
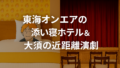
コメント