18歳CEOが起業した“広告×ゲーム”革命
2025年8月3日(日)の朝、フジテレビで放送される『発掘!スタートアップ ヒロミのおはようミーティング』では、18歳の若き起業家が登場します。番組では、ゲームと広告を組み合わせた新たなビジネスモデルを展開する株式会社EbuActionの代表が特集される予定です。彼がどのような経験から会社を立ち上げ、ゲーム内で企業とユーザーを結ぶ新しい方法を考え出したのか、注目が集まっています。
高校を離れてゲームの世界に飛び込んだ過去
彼は中学2年で学校を辞め、それ以降は不登校の時期を過ごしました。その間に夢中になったのがゲーム『Fortnite』で、6000時間以上もプレイを続けていたそうです。単に遊ぶだけではなく、eスポーツの運営や配信活動なども行い、ゲームと人のつながりを深く感じてきました。そうした中で、企業がゲームの中でどう存在感を出すかという課題に興味を持ち、15歳のときに起業。18歳の今では、すでに多くの企業とタイアップを重ねるプロフェッショナルとして活動しています。
ゲームと広告がひとつになる新しい仕組み
従来の広告は、バナーや動画など、画面の外側で情報を伝える形式が主流でした。しかし、EbuActionの仕組みは違います。ユーザーがプレイしているその瞬間に、自然に企業の世界観や商品に触れられるよう、ゲームそのものを広告の舞台にしています。RobloxやFortniteを活用して、キャラクターや設定の中にブランド要素を入れたり、遊びの中で社会的メッセージを伝えたりしています。
| 比較項目 | 従来の広告 | EbuActionの手法 |
|---|---|---|
| 表現方法 | 外部に動画やバナーを配置 | ゲーム内で遊びながら情報が届く |
| 体験のかたち | 一方通行で受け取る情報 | プレイヤーが自ら参加して感じ取る |
| 記憶への残り方 | 一瞬だけの視認 | 自分の動きと結びついて記憶に残る |
| 拡散性 | 広告としての制限が多い | SNSで自然と共有されやすい |
この仕組みの強みは、ユーザーが「広告を見た」とは感じず、「楽しいゲームをした中で企業と出会った」という体験を得られるところにあります。さらに、ゲームはSNSのように拡散されやすく、自然と話題になりやすいため、広告効果も高くなります。
実際のプロジェクトと反響
中でも注目されたのが、渋谷区と連携した『SHIBUYA Good Manner Challenge』というゲームです。これはFortnite上で制作されたもので、街中にゴミを捨てるとゾンビが発生するという設定になっています。プレイヤーはゾンビと戦いながら、マナーについて考える仕掛けがされています。10万人以上がプレイし、関連動画の再生数は60万回を超えました。企業や自治体にとっても、単なるCMでは届けられないテーマを伝える新しい手段として注目されています。
なぜ成功しやすいのか?若さと時代のマッチング
彼の強みは、プレイヤーとしての目線を持ちつつ、企業が求めるブランディングや訴求の方法を理解している点にあります。ゲームがSNSと融合し始めている今、「体験が広告になる」という考え方はZ世代にとても合っています。しかも、こうした仕組みはまだ大手広告会社でも本格参入していない分野で、今がまさにチャンスの時期です。テレビ番組で紹介されたことも大きな信用になり、信頼の輪も広がりやすくなっています。
未来の目標とこれからの広がり
EbuActionの代表が目指すのは、国内だけでなく世界を舞台にした展開です。将来的には最年少での株式上場も視野に入れ、次世代マーケティングの旗手としてのポジションを狙っています。ゲームが広告になるという考え方は、今後さらに広がっていく可能性があり、教育や福祉など社会的な分野への応用も期待されています。
まだ放送前ですが、18歳の若者が自らの経験を活かして会社を立ち上げ、新しい市場を作っているという事実だけでも、十分に注目に値します。放送では、彼がどんな思いで会社を作り、どんな苦労を乗り越えてきたのか、そして今後どんな未来を描いているのかが語られるでしょう。放送後にはさらに内容を追記していく予定ですので、チェックしておきたい一回です。
Z世代に刺さる“ゲーム的広告”の構造とは?

ここからは、私からの提案です。Z世代は、広告を「見るもの」ではなく「遊ぶもの」として受け取る傾向が強くなっています。スマホやSNSに慣れた彼らは、単なる一方通行の広告よりも、自分で操作しながら参加できる“体験型の広告”に強く反応します。そのため、広告そのものがゲームの一部として組み込まれるような仕組みが、Z世代にとって自然で受け入れやすいスタイルとなっています。
操作から始まるインタラクティブな導入
ゲーム的広告は、まず「タップして始める」「スワイプで進める」など、ユーザーの能動的な操作からスタートします。テレビCMやWebバナーのように一方的に表示されるのではなく、触って動かせることで、広告が遊びの延長として自然に受け入れられます。Z世代は画面の中に触れることが当たり前の世代なので、動きのある導入が好まれやすいです。触った結果がすぐに画面に反映されることで「自分が広告を動かしている感覚」が生まれ、それが共感につながっていきます。
自分で選べるオプトイン型の参加設計
見せられる広告ではなく、「遊んでみたいかどうか」を自分で選べる構造がZ世代にとって重要です。多くのゲーム広告では、動画を見ることでゲーム内通貨や特典がもらえるオプションが用意されていますが、Z世代はこのように選択肢を与えられるスタイルに心地よさを感じます。特にRobloxやFortniteでは、ユーザーが自ら参加し、遊ぶことでブランドに触れる「報酬付き広告」が好評です。広告の内容が“強制”ではなく“参加型”である点が、ブランド好感度の向上につながっています。
クリアで得られる報酬が購買意欲に直結
広告の一部としてミニゲームをプレイし、それをクリアするとアイテムやポイントがもらえる仕組みがよく使われています。これにより、Z世代はゲームの達成感を味わいながら、広告体験も楽しめます。成功体験と報酬が記憶に残りやすく、次第にそのブランドやサービスへの好印象が形成されていきます。実際にインタラクティブ広告は、従来の静止型広告に比べて倍以上の視聴時間や滞在率を記録するケースもあり、マーケティング効果も高くなっています。
SNSでの共有がブランド拡散に直結
報酬を得たり、ゲーム自体が面白かったりすると、Z世代は自然とその体験をSNSに投稿します。とくにスクリーンショットやプレイ動画は、X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどにシェアされやすく、そこからのUGC(ユーザー生成コンテンツ)として拡散が広がります。企業側が大きな広告費をかけなくても、ユーザー自身が“広告塔”になってくれるというのが大きなポイントです。しかも、Z世代はUGCに高い信頼を持っているため、広告よりも自然にブランドが広まっていきます。
体験を通じて生まれるブランドとのつながり
一連の仕組みの中で、広告は単なる“情報”ではなく“思い出”や“体験”として残ります。Z世代にとっては「遊んだ記憶」が「そのブランドとの関係性」を作っていくのです。企業ロゴをただ見るより、ゲームの中でキャラクターと協力したり、ブランドをテーマにしたアイテムを操作したりすることで、より深くブランドを覚えてもらえるようになります。娯楽と広告が完全に融合したこの形は、今後のスタンダードになっていく可能性があります。
| 段階 | 内容 | Z世代に刺さる理由 |
|---|---|---|
| 体験開始 | タップやスワイプで自分から広告を始める | 自分で動かす=主導権があると感じやすい |
| オプトイン型ミニゲーム | 「やる・やらない」を選べる報酬付き広告 | 強制感がなく、自由に選べることでストレスが少ない |
| クリア=報酬ゲット | プレイ後にポイントやアイテムがもらえる | 達成感と報酬が記憶に残る |
| SNSでの共有 | 経験をスクショや動画でシェア | 楽しさがリアルタイムで広がる、UGCも生まれる |
| ブランドとの親近感 | 体験が記憶に残り、自然に企業名や商品に興味が湧く | 「遊びの中で出会った」から好印象になりやすい |
Z世代に向けた広告を考える際、ゲームの持つ「操作性」「共有性」「達成感」といった要素を広告の中に取り入れることで、より自然にブランドとの接点を作り出すことができます。広告が嫌われるのではなく、むしろ好かれる体験へと進化しているのです。

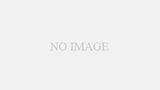
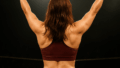
コメント