千葉の山奥で共同生活する男女3人の秘密とは?元アニメプロデューサーの選んだ生き方
2025年6月12日(木)放送のテレビ東京『ナゼそこ?』(20:58~21:54)では、千葉県の山奥で謎の共同生活を送る若い男女3人に密着しました。家族でも恋人でもない彼らが、なぜ赤の他人同士で山の中に住んでいるのか。その背景には、それぞれが歩んできた人生と心の変化がありました。今回の放送では、現代社会を離れ、自然と向き合いながら暮らす3人のリアルな姿が映し出されました。
千葉の山中で始まった不思議な暮らし
番組が訪れたのは、千葉県の山あいにひっそりと佇む1軒の古びた納屋。ここに暮らしているのは、清水陽介さん、廣瀬亜梨沙さん、前島恭兵さんの3人です。彼らは家族でも恋人でもなく、かつて専門学校で教える側と学ぶ側だった、いわば先生と生徒という関係でした。そんな3人がなぜ一緒に暮らしているのか。それは清水さんのある決断がきっかけでした。
清水さんはもともとアニメ制作のプロデューサーとして働いており、手がけた作品の中には累計1200万部を超える人気漫画のアニメ化も含まれていました。都心での仕事と生活をこなす中、年収は700万円以上という安定した生活を送っていました。しかしコロナ禍を経て、仕事に追われる日々の中で体調を崩し、生活にも支障をきたすようになります。
-
身体よりも仕事を優先していた生活に限界を感じた
-
自然の中で、心と体をリセットしたいという思いが芽生えた
-
最終的に「自分のために生きる」ことを選び、千葉県の山奥に移住
住まいに選んだのは、人里から離れた山中の納屋。そこに縁もゆかりもない土地ながら移住し、廣瀬さん・前島さんと共同生活を始めました。建物は傷みがひどく、3人でコツコツと改装して住める状態に整えました。現在の暮らしは、最低限のインフラと自力で整えた設備に支えられています。
-
電気はソーラーパネルでまかない、天候が悪い日は節電して対応
-
水は山水を直接引き込み、飲み水や風呂の水として活用
-
ガスは使用せず、薪を割って燃やす生活を選択
特に目を引いたのは、手作りの風呂小屋。お湯は山水を薪で温めて使っていましたが、当初は12時間かけてようやく沸くという非効率な状態でした。そこで清水さんが考案したのが「蓄熱板」。これにより、晴れた日なら約1時間で湯が沸くようになり、生活の質が大きく向上しました。
彼らの暮らしぶりは、都会での便利さとはかけ離れているかもしれませんが、自ら手を動かし、環境と向き合う中で得られる満足感と実感は確かなものでした。清水さんは、かつての自分が「仕事で結果を出すことばかりを追い求めていた」と振り返り、今は「小さな工夫で今日が少し良くなることの積み重ねがうれしい」と話していました。
3人が過ごす納屋は、完全な自給自足とはいかないまでも、自然とともに暮らす知恵と手間を大切にした“今の自分たちにちょうどいい”生活です。縁のなかった土地で始まったこの暮らしは、どこかぎこちなくもありながら、確かに根を張りつつありました。目立つことも華やかさもないけれど、人と自然との関係を見つめ直す静かな暮らしが、そこにはありました。
仲間となった教え子たちの過去と決断
清水陽介さんと共に千葉の山奥で暮らす廣瀬亜梨沙さん、前島恭兵さんの2人は、かつて清水さんが教えていた専門学校の生徒でした。それぞれが異なる人生の転機を経験し、最終的に自然と再会し、今の共同生活へとつながっていきました。
前島さんは長野県出身。上京後、慣れない生活や心身の負担からうつ状態となり、食事も摂れず家から出られない時期が続いていたといいます。体調が少しずつ回復してきたころ、友人の卒業公演の舞台を観に行き、出演者の楽しそうな姿に胸を打たれたことで、自分の人生に再び意欲を取り戻すようになりました。そして、声優を志し専門学校に入学。そこで出会ったのが当時先生をしていた清水さんでした。
廣瀬さんも同じ専門学校の卒業生で、すでに声優として活動していた時期がありました。けれど、都市での生活に違和感を抱き、精神的な疲労感や孤立感を感じるように。そうした心の変化から、自然の中での暮らしに目を向けるようになりました。やがて清水さんとの再会がきっかけとなり、3人の共同生活が始まりました。
-
3人は、住まいを整えるだけでなく敷地内で農作業にも取り組み、畑では年間を通じて10種類以上の野菜を育てている
-
果樹(きんかん・レモン・みかん・梅など)も栽培し、収穫後はジャムやシロップなど保存食に加工するなど、生活の幅を広げている
-
この日は山でタケノコを2本収穫し、ホイル焼きにして囲炉裏で焼き、みんなで味わっていた様子も紹介された
こうした暮らしは、ただ不便なだけではありません。エネルギーも薪や太陽光を使い、冷暖房や照明、調理に活用。特に電気の使い方には工夫が必要で、天候によって使える量が変わるため、無駄を出さない知恵と計画性が求められます。
また、日々の食生活のほとんどを畑や山の恵みから得るため、スーパーに通う回数も最小限。0円生活に近いスタイルを実現するため、日々の暮らしそのものが学びと実験の場になっています。食材を得る苦労も喜びに変えるこの生活は、都市生活では得がたい生きる手応えを感じさせてくれるものでした。
廣瀬さんと前島さんにとって、ここでの暮らしは、かつて自分を追い込んでいた環境からの脱却であり、新たな価値観に出会うきっかけにもなっているようです。かつては教室で向き合っていた3人が、今では山の暮らしを通じて同じ時間を分かち合い、支え合いながら、新たな人生を築いていました。華やかさはないものの、心と身体が寄り添える居場所としての山の暮らしが、静かに息づいていました。
それぞれが求めた「人の温かさ」と「生きる場所」
千葉の山奥で始まった共同生活は、3人にとってただの移住ではなく、それぞれが心の奥で求めていた「本当の居場所」を見つける旅でもありました。清水陽介さんがこの地を選んだ理由について語ったのは、周囲に民家がなく、土地が広く、何より近所の人がとても親切だったという点でした。孤立した環境に見えるこの場所こそが、清水さんにとっては人との新しいつながりを感じられる場所だったのです。
-
無理に誰かと関わることもなく
-
自分のペースで生活を整えることができる
-
必要なときには近所の人が手を差し伸べてくれるあたたかさがある
自然に囲まれ、毎日山や畑と向き合う生活の中で、心身の緊張が解け、都市生活で荒んでいた心が少しずつ癒やされていったといいます。
前島恭兵さんは、声優の仕事が東京中心で行われている中、仕事の数が減ったことで生活スタイルを見直す必要がありました。**「千葉に住みながら東京に通うほうが現実的で効率的」**という判断が、移住の大きなきっかけとなりました。交通手段を工夫すれば、都心と自然を両立できる生活が成立することに気づき、新しい働き方と暮らし方のバランスを模索するようになりました。
廣瀬亜梨沙さんは、都市での生活ではなかなか気づけなかったことに、山の暮らしの中で出会ったと話していました。忙しさの中で当たり前だった人との関わりが、自然の中で少しずつ再確認され、改めて「人のありがたみ」を感じるようになったと語っています。
-
小さな会話や助け合いが日常にあること
-
ご近所から分けてもらう山菜や情報
-
一緒にごはんを作り、食べる時間の中で生まれるぬくもり
こうした日々の積み重ねが、都市では見えづらくなっていた人のやさしさや、**「誰かと生きることの意味」**を感じさせてくれるといいます。
この山での暮らしは、便利さや快適さではなく、「気持ちが休まるか」「自分が素直でいられるか」ということが大切にされています。それは3人にとって、生き方そのものの問い直しでもありました。便利な都市からあえて距離を置き、心が穏やかに過ごせる場所を選んだことが、今の自分たちにとって最良の選択だったと、それぞれの言葉や表情から伝わってきました。
まとめ
この日紹介された3人の姿は、決して“特別な生き方”ではなく、今の時代に失われがちな人とのつながりや、自然との関係を取り戻す試みでもありました。技術や都会の便利さに囲まれた暮らしの中で、改めて“心地よさ”とは何かを見直すきっかけになるエピソードでした。
次回の放送でも、常識の外で暮らす人々の「ナゼ?」に迫るストーリーが期待されます。


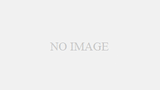
コメント