お正月の風物詩「お年玉」の変化に迫る!2025年の最新事情
2024年12月27日放送の日本テレビ「ZIP!」では、お正月の定番イベントである「お年玉」をテーマに、2025年の最新トレンドについて深掘りしました。お年玉の金額や渡し方が時代とともに変化している現状を、調査結果や最新データを交えながら紹介。子どもたちの期待や親世代の実情、キャッシュレス化の進展がどのように影響を与えているのかを詳しく解説しました。
お年玉の由来は御歳魂から
御歳魂というのは、正月に歳神(年神)を迎えるためにお供えされた丸い鏡餅のことを指しており、お供えした後に家族に分け与えられていました。 また、その餅は年神の生命ともされており、家族に分け与えることで一年を無事に過ごせるように祈るという宗教的な一面もあります。2022/12/15
2025年、お年玉の金額はどう変わるのか?
子どもたちの希望額と現実のギャップ
2025年を迎えるにあたり、子どもたちが希望するお年玉の金額について調査が行われました。多くの子どもたちは「5,000円から10,000円程度」を希望しており、特に年齢が上がるにつれて高額を期待する傾向が見られます。一方で、物価高や家計への負担増から、親世代が実際に渡せる金額には限りがあるのが現状です。このギャップが家庭内での話題になることも多く、家庭ごとの「お年玉ルール」も注目されています。
年代別の渡し方の工夫
40代~60代の親世代では、複数の子どもにお年玉を配る際の工夫として「人数分を均等に分ける」「上の子には少し多めに渡す」などの方法が主流です。これは、子どもの年齢や成長に応じて金額を調整する一方で、全体の負担を抑えるための策でもあります。また、祖父母世代においては、「孫全員に平等に渡す」という考えが根強く、兄弟間の不公平感をなくすための努力が見られます。
時代別データで見るお年玉の使い道
学研教育総合研究所のデータでは、2014年と2024年を比較すると、お年玉の使い道に大きな変化が見られます。2014年当時は「ゲームやおもちゃの購入」が主流だったのに対し、2024年には「貯金」が最も多い回答となりました。これは、家庭教育の変化や子どもたち自身の将来設計への意識向上が背景にあります。2025年も同様の傾向が続くと予想されており、「お年玉での自己投資」や「必要な物だけに使う」といった節約志向も広がっています。
キャッシュレス化が進むお年玉の渡し方
キャッシュレス決済の普及と実態
キャッシュレス化が進む中、お年玉の渡し方にも新しい流れが生まれています。番組では、電子マネーを活用したお年玉の送金方法について調査結果が発表されました。2023年には電子マネーでの送金率がわずか3.6%だったのに対し、2025年にはその割合が7.6%に増加すると予測されています。
特に、若い親世代ではPayPayやLINE Payといったスマホ決済を利用してお年玉を渡すケースが増えています。これにより、現金を用意する手間が省けるだけでなく、送金履歴が残るため管理がしやすいというメリットがあります。
キャッシュレス化の課題と展望
一方で、キャッシュレス化には課題もあります。特に高齢者世代にとっては「現金を直接渡す温かみが失われる」「スマホ操作が難しい」といった声が挙がっています。また、キャッシュレス化が進むことで、子どもたちが「お金の重み」を実感しにくくなる可能性も指摘されています。
2025年にはこれらの課題を解決するため、電子マネーの利用ガイドや子ども向けの金銭教育プログラムがさらに広がることが期待されています。
家族だけで過ごすお正月がもたらすお年玉文化の変化
コロナ禍以降の変化と家族間の関係
コロナ禍をきっかけに家族だけでお正月を過ごす家庭が増えたことも、お年玉文化に影響を与えています。以前は親戚一同が集まり、その場でお年玉を手渡すことが一般的でしたが、現在ではオンラインでの送金や郵送でのお年玉が増加しています。
お年玉と家族のつながり
このような変化の中で、「お年玉を渡す」行為自体が家族間の絆を深める重要な役割を果たしているという意見もあります。たとえキャッシュレス化が進んでも、「手渡し時の感謝の言葉を添える」や「メッセージ付きで送金する」など、コミュニケーションを大切にする工夫が必要です。
まとめ
お年玉の金額や渡し方は、社会や家族の変化に合わせて進化しています。2025年には、キャッシュレス化がさらに進むと予測される一方で、伝統的な温かみを保つ工夫も求められます。

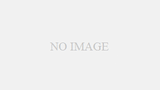

コメント