命をつなぐ挑戦「move your heart 医療機器開発に挑む医師」
生まれつき心臓に病気を持つ子どもたち。手術で一命をとりとめても、成長に合わせて何度も再手術が必要になるケースが多いのをご存じでしょうか。親にとっても子にとっても大きな負担です。「なぜ交換不要の医療機器がないのか?」と疑問を抱く方もいるでしょう。本記事では、大阪医科薬科大学病院の小児心臓血管外科医・根本慎太郎医師の挑戦に迫ります。この記事を読むことで、医療の裏側にある現実と希望を知ることができます。
子ども用パッチの問題点と家族の苦悩
先天性心疾患は生まれつき心臓に異常を抱える病気で、およそ100人に1人の割合で見つかるといわれています。心臓の壁に穴があいていたり、血管が狭くなっていたりと症状はさまざまですが、手術を受けなければ命に関わることも少なくありません。
その手術で使われるのが修復用パッチです。しかし、このパッチには大きな問題があります。素材が伸びないため、子どもの体が成長すると心臓に合わなくなり、さらに体内で異物反応を起こして固まってしまいます。その結果、手術からわずか2年ほどで交換が必要になるケースが多いのです。
大阪府枚方市に住む加藤廉基くんもその一人です。生まれてわずか13日目で最初の心臓手術を受けました。成長に合わせて心臓の状態も変化し、ついに15歳の時に再手術を受けることになりました。
一度目の手術でさえ家族にとっては大きな決断でしたが、再び胸を開きメスを入れる恐怖と負担は、本人にとっても家族にとっても計り知れないものです。成長期に繰り返される再手術は、心身の負担だけでなく生活や学校にも大きな影響を与えてしまいます。
「ガウディプロジェクト」の始動
根本慎太郎医師は、子どもたちと家族を苦しめる「繰り返しの再手術」という現実を変えるため、思い切って「交換不要のパッチ」を自ら開発しようと決意しました。
しかしその道は平坦ではありません。日本の医療機器の約7割は輸入品に頼っているのが現状で、特に子ども用医療機器は採算が取れず、企業にとっては利益になりにくいため、多くが開発に後ろ向きでした。根本医師は国内外の企業に何度も協力を求めましたが、10社以上から断られる厳しい現実が待っていました。
そんな中で出会ったのが、福井県福井市の繊維メーカー・福井経編興業でした。社長の高木氏は、実際に小児心臓の手術現場を見学し、胸を大きく揺さぶられました。小さな体で必死に生きようとする子どもたちの姿を前にして「二度と同じ苦しみを繰り返させたくない」と強く心を動かされ、なんと7000万円以上を投じて無菌室を設置することを決断したのです。
こうして、地方の繊維メーカーと一人の外科医がタッグを組み、社運をかけた挑戦、「ガウディプロジェクト」が動き出しました。
医療現場と企業の連携
開発を進める上で欠かせなかったのは、強度と柔軟性を両立した特殊な生地でした。赤ちゃんから大人になるまで成長に合わせて伸び、なおかつ心臓の動きに耐えられる強さも必要とされる――非常に難しい条件です。そこで挑んだのが、福井経編興業の技術者・櫻井潤さんでした。繊維分野の経験は豊富でも、医療分野はまったく未知の世界。それでも「子どもたちを救いたい」という思いを胸に、試行錯誤を重ねました。
一方で、医療機器の開発には技術だけでなく、資金力と企業の後押しが不可欠です。根本医師は大手の帝人に協力を依頼しましたが、最初はリスクの高さから慎重な姿勢でした。転機となったのは、役員が実際に心臓手術の現場に立ち会ったこと。目の前で命を救う真剣な場面に触れ、根本医師の情熱と必要性に心を動かされ、ついに参画を決めました。
さらに根本医師は、日本国内にとどまらず海外市場も見据えた戦略を描いていました。開発コストを回収し、多くの子どもたちに届けるためには国際的な展開が不可欠。そこで根本自ら海外に足を運び、現地の専門家や企業に営業活動を行いながら、プロジェクトを世界へ広げていきました。
シンフォリウム誕生とその意味
開発に携わった技術者たちが導き出した答えは、あえて「溶ける糸」を使うという発想でした。特殊な編み方で2種類の糸を組み合わせ、一方は体内で徐々に吸収され、もう一方は吸収されずに残る仕組みを考案。この工夫によって、しなやかさと強度を両立させ、成長に合わせて心臓の動きに順応できる画期的なパッチが誕生しました。
臨床試験では安全性が確認され、2023年7月に国の正式な承認を獲得。新しいパッチには「シンフォリウム」という名前が与えられ、1枚あたり37万8560円で販売が開始されました。価格だけを見れば高額に感じられますが、再手術の回数を減らせることを考えれば、子どもと家族にとって大きな負担軽減につながります。
2025年時点でシンフォリウムは185人の命を支えており、アメリカでの販売も目前に迫っています。すでに実際の医療現場で活躍しており、将来はさらに多くの国へと広がる可能性があります。
その中でも象徴的だったのが、優茉ちゃん(当時1歳)のケースです。彼女はシンフォリウムを用いた初めての手術を受け、心臓にあった2つの穴を塞ぐことに成功しました。従来のパッチのように短期間で交換を迫られる心配が少なくなり、成長とともに過ごせる時間が大きく広がったのです。
シンフォリウムは、子どもたちの未来に「再手術を減らせる希望」を確かに示しました。
医師としての原点と家族の支え
根本慎太郎医師の挑戦の出発点には、深い家族の経験がありました。次男の諭くんは、生まれつき染色体異常を抱え、さらにがんとの闘病生活を余儀なくされました。視力を失いかけながらも、何度も手術を受け、懸命に生き抜こうとする姿は、家族にとってかけがえのない日々でした。
しかしその努力もむなしく、諭くんはわずか8歳でこの世を去ることになります。突然の別れは家族に大きな悲しみを残しましたが、同時に根本医師の胸に「残された力を世の中の役に立てたい」という強い決意を芽生えさせました。その思いが後に、子どもたちの未来を変える医療機器開発へとつながっていったのです。
現在、長男の清正さんは父と同じ道を選び、医師として働いています。三男の直広さんも大学院で学びながら父を支え、家庭でも医療現場でも力を合わせる姿勢は、まさに「親子で挑戦を受け継ぐ」形となっています。
こうして、家族で支え合いながら歩んできた根本家の姿は、単なる個人の挑戦にとどまらず、次世代へと受け継がれる希望の物語になっています。
未来への挑戦と世界への広がり
根本慎太郎医師は「交換不要のパッチ」に続く次なる挑戦として、現在は「人工弁の開発」に取り組んでいます。子どもの心臓に適した人工弁は世界的にも開発が難しく、承認まで長い年月がかかる高いハードルの分野です。
2025年には動物実験がスタートし、その場には協力企業である帝人の技術者も立ち会いました。医師と企業が一体となって歩む姿勢は、日本の医療機器開発に新しい風を吹き込んでいます。
現実として、国内でこれまでに承認された小児用医療機器は529例中わずか12例(2.2%)にとどまっています。採算性の低さやリスクの高さから、企業がなかなか参入しにくい領域であり、それだけに根本医師の挑戦は非常に価値のあるものだといえます。
さらにこの挑戦は、医療の現場を超えて教育の場にも波及しました。大阪・関西万博の探究学習では、根本医師の取り組みを知った小学生たちが自ら学びを深め、未来に向けて発表する活動が広がっています。子どもたちの探究心に火をつけ、次の世代の研究者や医師を育むきっかけとなっているのです。
そして今、根本医師の活動は日本だけにとどまりません。インドネシアの学会でも研究成果を発表し、国境を越えて注目を集めています。世界中の子どもたちに医療の希望を届けたい――その思いは確実に広がり続けています。
まとめ:根本医師の挑戦が示す未来
-
子ども用医療機器は採算が取れず開発が難しい
-
福井経編興業や帝人の協力により「シンフォリウム」が誕生
-
185人以上の命を救い、アメリカでも販売予定
-
次なる挑戦は人工弁の開発で、未来世代へバトンをつなぐ
根本医師の取り組みは、まさに「医師の情熱が産業を動かす」ことを証明しています。あなたもこの記事を通じて、日本発の医療イノベーションの重要性を知り、関心を持ってみませんか。未来を変える挑戦は、今この瞬間にも続いています。
出典:NNNドキュメント(2025年9月15日放送)

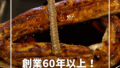
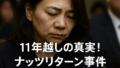
コメント