「街の“清潔”を守る!掃除のプロに密着」
毎日当たり前のように清潔に保たれている街。でも実は、その裏にはたくさんのプロの努力があることをご存じでしょうか?2025年8月4日放送の「よじごじDays」では、そんな“掃除のプロ”たちの現場に密着。鉄道・百貨店・美術館といった場所で活躍する清掃員たちの工夫や最新テクノロジー、さらには家庭で役立つ掃除の裏ワザまで、驚きと発見がたっぷり詰まった内容が届けられました。
鉄道を守る!プロ清掃員の道具と技術
まず紹介されたのは鉄道の清掃現場。たくさんの人が行き交う駅や車内を毎日キレイに保つために、プロたちはどんな工夫をしているのでしょうか?注目されたのは、汚れを浮かせてから吸引する特殊な清掃機器。床の隙間やシートの細かい繊維の奥に入り込んだホコリも逃さずキャッチできる優れものです。また、終電後から始まる「時短で高精度」な清掃スケジュールも紹介され、緻密に管理された作業の様子に驚きました。
最新ロボが活躍!百貨店のキレイを保つ秘密
次に取り上げられたのは、百貨店の最新清掃事情。特に注目されたのは自動運転型のお掃除ロボットです。営業時間外に床を巡回しながら、ホコリやごみを吸い取るロボットは、障害物を避けるセンサーも搭載されており、人気のフロアでも安心して使えるとのこと。作業の効率化だけでなく、スタッフの負担を軽くする役割も担っている点が強調されていました。
美術館の展示を守る繊細なカーペット清掃術
静かな空間が求められる美術館では、音も埃も出さない清掃が必須です。ここで紹介されたのは、カーペット専用の静音バキューム機と微細な粒子を取り除く手作業の拭き取り。美術品にホコリが付かないよう、館内は常に空気と床の清潔が保たれています。来館者が気づかないうちに、職人技がいかに生かされているのかが丁寧に描かれていました。
家でも使える!掃除のプロが教える裏ワザ
番組の最後には、家庭で簡単に試せる掃除テクニックも紹介されました。特に好評だったのが、使い古した歯ブラシと重曹水を使ったサッシ掃除の方法。汚れを浮かせて落とすだけでなく、カーテンレールのホコリ落としにはストッキングをかぶせたハンガーを使うなど、身近な道具でできる工夫が盛りだくさんでした。
以下の表に、番組で紹介された家庭で応用できる掃除テクニックをまとめました。
| 掃除場所 | 使用道具 | ポイント |
|---|---|---|
| サッシ | 歯ブラシ+重曹水 | 汚れを浮かせてから拭き取ると効果的 |
| カーテンレール | ストッキング+ハンガー | ホコリを絡めとることができる |
| シンク周り | アルミホイル+水 | ヌメリ対策に効果あり |
| フローリングの隅 | 綿棒+中性洗剤 | ピンポイントで汚れを落とせる |
どれも簡単に取り入れられる方法ばかりで、番組を見ながら「すぐ試したい」と感じた視聴者も多かったことでしょう。
プロの技術と新しい技術が組み合わさって、私たちの街の清潔が保たれていることがよくわかる放送内容でした。身近な掃除も、少し視点を変えればぐっと効率よく、楽しくなるかもしれません。
家でも使える!掃除のプロが教える裏ワザ
よじごじDaysでは、鉄道・百貨店・美術館の清掃現場で使われているプロの技術や工夫を、家庭でも真似できるようにアレンジした実用的な裏ワザが数多く紹介されました。ただ掃除が上手というだけでなく、安全に、効率よく、手間なくできるようにするための小さな工夫が詰まっており、誰でも取り入れやすい内容になっています。
毎日少しずつやる掃除で家がきれいに
掃除は一度にまとめてやるよりも、「毎日5分」でできることを少しずつ行う方が続けやすくなります。たとえば、朝の洗面のついでに鏡を拭いたり、夜の料理のあとにシンクをさっと洗ったりするだけでも清潔な状態が長く保たれます。プロの清掃員も実際に「スキマ時間を活かしたルーティン掃除」を取り入れており、家でも同じ考え方を応用できます。
また、お風呂上がりに床をシャワーで軽く流すだけで、カビの発生が抑えられるという習慣も紹介され、特別な洗剤を使わなくても予防できる方法として注目されました。
家庭でも使えるプロ流の工夫がいっぱい
鉄道清掃で使われていた粘着板による羽毛の除去は、静電気でホコリを吸着する市販の吸着モップでも代用できます。また、折りたたみ式のブラシや、背中にしょって使う掃除機のような道具は、軽量で収納しやすい家庭用掃除グッズに置き換えて使えば、掃除がもっとラクになります。百貨店で活躍している清掃ロボットの例を参考にするなら、家庭では薄型で静音性にすぐれたロボ掃除機を選ぶとよいとされていました。吸引力だけでなく、家具の下まで入れる設計を重視するのがポイントです。
汚れのタイプに合わせた掃除の順番も大切
プロは、汚れの種類によって掃除の順番を変える工夫もしています。たとえば、キッチンのシンクは「油汚れ→水アカ→除菌」の順番で掃除すると、汚れが重なって落としにくくなるのを防げます。これは家庭でもすぐに実践可能で、順序を間違えると逆に汚れが広がってしまうこともあるため、正しい手順がきれいへの近道になることが分かります。
以下のような掃除例を参考にすると、家庭でもプロ並みに効率よく掃除ができます。
| 掃除する場所 | 道具や方法 | ポイント |
|---|---|---|
| シンク | 重曹 → クエン酸 → 漂白剤 | 汚れの順に処理すると落ちやすい |
| お風呂の壁 | 歯ブラシ+カビ取り剤+ラップ | カビの根まで届きやすくなる |
| 換気扇 | 重曹湯に部品をつけ置き | 油汚れが浮いて取りやすい |
| 鏡・洗面台 | マイクロファイバークロス | 毎朝の水拭きで水アカ防止 |
| フローリング | 静電モップでさっと1回 | 毎日1分でホコリがたまりにくい |
プロの「段取り」をまねしてみよう
プロの清掃員が大切にしているのは、順番を決めて無駄なく動くことです。たとえば、駅構内では歩きながら紙ゴミを回収し、次に床をブラシで掃除するという一筆書きのような流れを作ることで効率がアップします。家庭でも、「洗面所のあとにトイレ」「トイレのあとにお風呂場」など、動線を意識して掃除することで移動の手間や時間を短縮できるようになります。
このように、プロの清掃技術は「道具」だけでなく「順番」や「流れ」にも秘密があります。家庭で無理なく応用できる部分を取り入れることで、掃除がもっとスムーズになり、毎日の生活が快適に変わっていきます。


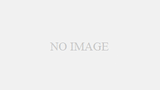
コメント