“楽しい”を仕事に変えた起業家・山本正喜の挑戦
2025年8月4日放送のテレビ東京「夢遺産」では、ビジネスチャットツール「Chatwork」の生みの親であり、現在はBPaaSサービス「kubell」を展開する社長・山本正喜さんの人生に迫りました。今回の特集では、山本さんがどのようにして「楽しい」を仕事に変え、どんな想いで今の事業を育てているのかが描かれました。短い放送ながらも、起業の裏側や価値観がぎゅっと詰まった内容でした。
少年時代から芽生えた“創る楽しさ”
大阪で生まれ育った山本さんは、小学生のころに親が使っていた古いパソコンをさわったことがきっかけでプログラミングに夢中になりました。BASICという言語を独学し、友人と一緒にゲームを作るうちに「自分で創るってこんなに楽しいんだ」と気づいたそうです。この体験が、今につながる“楽しい”の原点でした。
大学は電気通信大学の情報工学科に進学し、ちょうどインターネットが一般に広まりはじめた時代。毎日のようにプログラムを書き、大人たちと一緒にビジネスを作る環境にのめり込みました。このころから、遊びではなく「働くこと=楽しい」という考えが自然と身についていったといいます。
Chatwork誕生までの道のり
2000年、山本さんはお兄さんと一緒に「EC studio」を設立。起業したばかりのころは、社員も少なく予算もほぼゼロ。しかし、当時としては画期的だったリアルタイムのブラウザチャットツールをつくり、それが後の「Chatwork」へとつながります。
2011年、正式にChatworkをリリース。チャットを使った業務の効率化は、企業からの反響も大きく、一気に利用者が拡大しました。
しかし順風満帆というわけではありません。アクセス解析ツールの開発で約2年の時間とリソースを費やした結果、思ったような成果が得られず、会社の経営は厳しくなります。その苦境の中で、山本さんはChatworkを“たった一人で”押し進めるという決断を下しました。社内の反対もある中、責任を背負ってプロジェクトを推し進めたことで、会社の転機となる成功へとつながっていきます。
社名を「kubell」へ、そしてBPaaS時代へ
2018年にCEOとなり、2019年にはChatworkが上場。その後、山本さんは「働くをもっと楽しく、創造的に」という新たなミッションを掲げ、企業文化そのものを見直していきました。そして2024年、会社名を「Chatwork」から「kubell」へ変更。SaaS企業としての道から、BPaaS(Business Process as a Service)へ本格的にシフトしました。
「Chatwork アシスタント」や「タクシタ」などのサービスを通じて、総務・経理・労務といった“やる必要はあるけれど創造性が発揮しづらい仕事”を、AIと人の力で代行。社員が本当にやりたいこと、自分にしかできないことに集中できるよう支援しています。
「楽しい」と「楽」は違う
山本さんは、「楽しい仕事」を増やしたいと考えていますが、それは「楽な仕事」とはまったく違うと話しています。自分が本気で取り組めること、目の前の課題に夢中になれること、それこそが“楽しい”につながると信じているからです。
kubellの社内では、年齢や肩書きに関係なく、新しいことに挑戦したい人が手を挙げれば、まずやってみるという文化が根づいています。実際に若手がサービス責任者になったり、混沌とした立ち上げの場に自ら飛び込んだりすることも日常のように起こっています。
未来へ向けて
現在kubellは、中小企業の業務支援分野で国内トップを目指しており、すでに1000社以上がBPaaSユニットを導入しています。今後は、地方銀行との提携や、自治体との連携などを進め、より多くの中小企業の“働き方改革”を支える存在となることを目指しています。
そしてその原点には、山本さんの「楽しいってなんだろう?」という子どものころの素朴な好奇心があります。それを大人になっても大事にしながら、自らの仕事と組織を“楽しい”ものに変えていこうという姿勢が、kubellの企業づくりを支えています。
番組公式サイト:テレビ東京「夢遺産」
企業サイト:kubell株式会社 公式サイト【2025年8月時点】
追記
Chatwork時代とkubellの違いを図解で示し、BPaaSへの理解を深めるために
kubellの前身であるChatworkは、もともと「社内のコミュニケーション効率を上げる」ことを目的に開発されたチャットツールです。しかし現在のkubellでは、単に“話す・連絡する”だけでなく、経理・労務・総務などの業務そのものをChatwork上で完結させるという形へと進化しています。この違いをはっきり伝えるには、文章だけでなく視覚的に示すことが効果的です。
事業構造とサービス範囲の違い
Chatwork時代はSaaS(ソフトウェア提供型)に分類されるビジネスモデルで、企業が自社内で活用するツールを提供する立場にありました。一方、kubellはBPaaS(業務プロセス代行型)という新しい形で、企業の中にある業務自体をAIと人のチームでまるごと請け負うサービスです。この転換により、顧客はツールを“使う”から、“任せる”というスタンスに変わりました。
働き方の変化と社内文化の違い
Chatwork時代の社内は、エンジニアやデザイナーがプロダクト開発の中心でした。プロダクトごとの改善や機能開発が日々行われ、会社全体が“モノづくり”に集中していました。ところがkubellでは、業務を受け持つ「クルー」と呼ばれる人たちが各地に点在し、リモートで顧客のバックオフィス業務を支えるスタイルにシフトしました。社員がすべての業務をこなすのではなく、社内外の力を使って分業・最適化する考え方が根づいています。
実際の違いを視覚的に伝える図解案
下のような図表を活用することで、読者にも両社の違いがわかりやすく伝わります。
| 比較項目 | Chatwork(旧) | kubell(現) |
|---|---|---|
| ビジネスモデル | SaaS(ツール提供) | BPaaS(業務代行) |
| 顧客の関わり方 | 社内で自ら操作して使う | チャットで依頼→AIと人が処理 |
| 社員の役割 | 開発や機能改善が中心 | クライアント業務の設計・運用・改善に注力 |
| 提供範囲 | チャットやタスク管理などコミュニケーション領域 | 経理・労務・総務の実務全般(まるごと代行) |
| 主な特徴 | チャット効率・UI重視 | 業務設計+運用+改善の一体化サービス |
| 働き方 | 開発部門中心/固定オフィス勤務 | リモート勤務中心/柔軟な働き方(副業・地方も活躍) |
この図のように、Chatworkでは“操作して使う”ことが求められましたが、kubellでは“任せるだけ”で日々の業務が進んでいきます。人とAIが協力して業務の最適な設計を行い、実行まで行うことがkubellのBPaaSモデルの特徴です。
まとめとして伝えるべきこと
kubellは「Chatworkの進化版」として紹介されることが多いですが、実際はサービスの構造や提供価値が根本的に違うものになっています。こうした違いを図解でわかりやすく整理することで、読者や見込み顧客にもkubellの目指す働き方改革の本質が伝わりやすくなります。記事の中盤やまとめ部分にこの図解と補足を入れることで、検索流入だけでなく、実際の利用への関心も高まる構成となります。


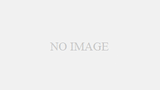
コメント