水卜アナが見た“令和の米づくり”のリアルと感動の現場
2025年はお米がニュースに登場する機会が増えています。『古古古米』が新語・流行語大賞にノミネートされ、新米価格の高止まりや全国共通おこめ券への注目など、私たちの食卓を支えるお米が話題の中心に立っています。今回のZIP!『ミトjob』では、水卜麻美アナが米農家の仕事を体験し、お米づくりの裏側と作り手の思いに触れました。
【月曜から夜ふかし】農家さんの個人的ニュース&茨城県民の日スペシャル AI農園夫婦の秘密と1時間睡眠キノコ農家の激務、茨城空港が人気の理由とは|2025年11月17日
黒川の田んぼへ到着 150年以上続く市川家の田んぼの歴史
ロケ地は神奈川県川崎市黒川。東京に近い地域ながら、自然と農地が広がる風景が残るエリアです。ここで迎えてくれたのは、150年以上にわたり田んぼを守り続けてきた米農家の市川さん。江戸時代から続く家系で、その土地の気候や土質まで熟知している“黒川の米づくりのプロ”です。
市川さんの田んぼは、季節によって風の流れを読むこと、田んぼの水量を一定に保つこと、稲の成長に合わせて手を入れることなど、細かな工夫の積み重ねで出来上がっています。毎年同じように見える稲でも、実はその年の天候に合わせて細かく調整してきた結果であり、長く続く農家ならではの経験が生かされています。
奨励品種『はるみ』とは?水卜アナも驚く粘りと香り
市川さんが育てている主力品種は、神奈川県が推奨する『はるみ』。このお米は、炊いた瞬間の香りが強く、冷めてもモチッとした食感が残るのが特徴です。お弁当やおにぎりに向いていると言われるのはこの性質のおかげで、時間が経ってもパサつきにくく、味が落ちません。
水卜アナも、収穫前の稲の香りや、籾の乾いた草のような穏やかな匂いに「これがごはんになるんだ」としみじみ感じていました。こうした生育途中の香りを感じることで、お米がただの食材ではなく“生きた植物”であることを実感できます。
あぜ道を手で刈る作業の大切さ
稲刈り体験は、まず鎌での手刈りから始まりました。大型の稲刈り機は田んぼの端まで入れず、あぜ道近くはどうしても人の手で刈る必要があります。鎌を握る角度や、稲の束を倒す方向など、初めての人にとっては意外と難しいポイントが多い作業です。
水卜アナは汗をにじませながらも、何度も姿勢を調整し、刈りやすい角度を市川さんに聞きながら繰り返していました。稲を刈るたびにカサッと音がして、独特の香りが広がる様子は、テレビ越しでも季節感を強く感じられる印象的なシーンでした。
稲刈り機の操作にも挑戦 “食卓を支える技術”の重み
次に挑戦したのは、いよいよ稲刈り機の運転。稲を自動で刈り取り、脱穀まで進めてくれる大型機械です。操作レバーは複雑ではないものの、まっすぐ進むこと、稲の列に合わせること、スピードを調整することなど、油断するとすぐに曲がってしまう難しさがあります。
市川さんは「機械でも人の感覚が大事」と話し、毎日同じように見えても田んぼの状態で微調整することが必要だと教えていました。水卜アナも緊張しながら慎重に操作し、稲が勢いよく機械に吸い込まれていく光景に驚きを隠せない様子でした。
令和の米騒動の裏側にある“現場の苦労”
今回の取材では、世間を騒がせた令和の米騒動にも触れられていました。
『古古古米』の流行語ノミネートや、新米の価格高止まり、政府が言及した全国共通おこめ券など、消費者側の話題が多い中で、農家はどう向き合っているのか。
市川さんは、気候変動や資材費の上昇によって年々コストが増えている現実や、品質を維持しながら収量を確保する難しさを語っていました。それでも、できる限りおいしいお米を届けたいという思いは強く、手作業と機械を組み合わせながら日々工夫していることが分かります。
収穫した『はるみ』を食べる瞬間に広がる幸せ
今回のロケのクライマックスは、収穫した『はるみ』の試食です。
炊きたての湯気が立つ白いごはんは、つやつやと光っていて、粒がしっかり立っています。水卜アナは一口食べた瞬間、「甘い」「香りが広がる」と声を漏らし、冷めてもおいしいという特徴を実感していました。
箸で持ち上げたときの粘り、噛んだときの弾力、鼻から抜ける優しい香り。生産者の思いと重なり、ただの“試食”ではなく“心に残る体験”として伝わってきました。
まとめ
ZIP!の『ミトjob』で紹介された黒川の米づくりは、2025年のお米を取り巻く状況を象徴する内容でした。
市川さんのように150年以上続く農家の努力は、私たちが当たり前のように食べているお米の裏側に確かに存在しています。
作り手の技術と思いを知ることで、毎日の食卓のごはんがより尊く感じられるはずです。
これから新米を選ぶとき、おにぎりを作るとき、誰かと食卓を囲むとき――今回の体験がふとよぎるような、そんな深い内容でした。
はるみをもっとおいしく炊くための下準備
浸水と洗い方の丁寧なステップ
お米は最初に軽く洗ってから、しっかり水を替えて洗い、仕上げにざるにあげて水気を切ります。ざるにあげる時間は15〜30分ほどがちょうどよく、ここで空気に触れさせることで粒が落ち着き、あとで入る水が均一になります。「万能鍋で炊くごはん」でも、このざる上げ15分以上が重要な工程として紹介されています。このひと手間が、炊き上がりの香りと食感を大きく変えてくるので、毎回欠かさず行いたいところです。
品種のはるみは、もともとつやが強くもっちりした特徴があるため、浸水をしっかり行うことでその良さがより際立ちます。浸水時間を長めに取ることで芯までしっかり水が入り、炊き上がったときの粒のまとまりや甘みが変わります。また、湯冷ましのやや冷たい水で浸水させると、夏場のように水温が高い時期でもむらが出にくく、安定した状態で吸水できます。実際に湯冷まし水を使っている家庭の例も紹介されていて、温度を意識して浸水する大切さが伝わります。
水分量の合わせ方
一般的な白米の炊飯では「1合に対して180〜200ml」が基本と言われていますが、はるみの場合は、もっちりした持ち味をより活かすために、少しだけ多めの水を加えるのが向いています。例えば、無洗米4合を870mlで炊くというレシピも見られ、800mlに加えて70mlを足すことで粘りとつやがしっかり出せるとされています。家庭の炊飯器や鍋でくせが違うため、「米の量×0.9〜1.0」を基準にしつつ、好みに合わせて5〜10%増やして調整すると、どの家庭でも安定した炊き上がりになります。水の量がしっかり合っていると、炊き上がりの立ち姿や粒の張りが違ってきます。
蒸らしと冷めたときのおいしさ
炊き上がったあとに10〜20分しっかり蒸らすことは欠かせません。鍋炊きの場合も同じ時間を取るように案内されていて、この蒸らしの間に余分な水分が落ち着き、粒の中にほどよく熱が入っていきます。蒸らしたあとはしゃもじで底からふわっと持ち上げるようにしてほぐします。これによって水分がほどよく飛び、冷めたときにもごはんがベタつきにくくなります。
はるみは冷めても硬くなりづらい品種なので、お弁当やおにぎりにぴったりです。炊き上がりの余熱で粒を落ち着かせることで香りが際立ち、一粒一粒に甘みがのります。炊き立てをすぐ食べたいときも、10分だけおいてから盛りつけると香りと旨みがしっかり立ちます。お弁当に使うときは、炊き上がったごはんを広げて表面を均一に冷ますことで、乾燥を防ぎつつおいしさを保てます。
保存と扱い方の工夫
昔ながらの米づくりをしている農家では、精米したあとできるだけ早く食べることを大事にしています。精米後の時間が短いほど香りやつやが保たれます。家庭でも、湿度の低い涼しい場所で保存すると状態が長持ちします。炊飯直前に室温に30分ほど戻すと、炊飯時の温度差が小さくなり吸水が安定して、仕上がりの粒感がそろいます。
こうした細かな手順を積み重ねることで、はるみ特有のつやと甘みが最大限に引き出されます。毎日のごはんがより楽しみになる炊き方です。

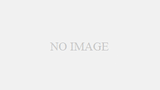
コメント