ジローラモが富山・砺波の米と職人文化を体感する旅
2025年7月20日放送の「遠くへ行きたい」では、ジローラモさんが富山県の砺波市と高岡市を訪れました。旅のテーマは「米王国で宝さがし」。自然とともに生きる人々の暮らし、伝統ある職人の技、地元の食文化にふれながら、ジローラモさんがさまざまな発見をしていく姿が描かれました。豊かな自然と人々のあたたかさにふれながら、米と鋳物という地域の魅力をあらためて感じられる内容となっていました。
散居村の風景に包まれて旅がスタート
ジローラモさんが最初に訪れたのは、砺波市にある散居村展望広場です。この場所からは、富山平野ならではの特別な景色「散居村(さんきょそん)」を見ることができます。水田の中に1軒ずつぽつんと家が建ち、その家々を囲むように木々が生い茂っています。この風景は昔ながらの農村の姿を色濃く残しており、日本でも珍しい景観です。四季折々で違う表情を見せてくれるため、地元の人々にとっても特別な場所です。
防風林に守られる家々と自然の暮らし
散居村の家のまわりには「屋敷林(やしきばやし)」と呼ばれる木々があります。これらは風を防ぎ、雪や日差しから家を守るだけでなく、昔は建材としても使われてきました。中でも青森ヒバは香りが強く、抗菌・防虫効果があることから、とても重宝されています。農家の新藤さんは、こうした自然との共生を大切にしながら暮らしていて、古い農具なども大切に保管されていました。
地元の農家レストランで味わう富山の食と文化
続いて訪れたのは、農家レストラン「大門」です。このレストランは、砺波市でとれたお米や野菜を中心に、地元の味を提供することにこだわって10年前にオープンしました。広い田んぼに囲まれたこのレストランでは、伝統的な家庭料理から現代風にアレンジしたメニューまでさまざまな料理が楽しめます。
イタリアの味「リーゾ・アル・フォルノ」を披露
レストランの厨房に立ったジローラモさんは、イタリア北部で親しまれている米料理「リーゾ・アル・フォルノ」を作りました。白米にトマトピューレを混ぜて、モッツァレラチーズ、サラミ、粉チーズを加えてオーブンで焼いた一品です。日本のお米の美味しさを活かしたアレンジで、訪れた人々にも喜ばれていました。
全国に種を届けた歴史ある米どころ
砺波のもう一つの魅力は、全国有数の種籾の生産地であることです。ジローラモさんは米農家の横山さんを訪ね、この地の歴史を学びました。昔、富山の薬売りが薬と一緒に種籾を持ち歩き、全国に米の文化を広めていったというエピソードも紹介されました。この地域で育てられるお米は、品質も高く、現在も日本中の田んぼへと広がっています。
江戸時代から続く富山の米の伝統
種籾の生産は江戸時代から始まり、昭和まで続く長い歴史を持っています。この地域で作られたお米の味の良さは、ジローラモさんも実際に味わって感心していました。単なる農業ではなく、知恵と努力が積み重なった成果であることが伝わってきました。
高岡で出会う職人たちの世界
旅の後半では、高岡市へ移動しました。ここは日本を代表する鋳物の町として知られており、400年以上の歴史があります。最初に向かったのは、町の象徴ともいえる「平和の鐘」です。誰でも自由に鐘を鳴らせるこの場所は、訪れた人の心を落ち着かせてくれる不思議な空間でした。
金屋町で感じる鋳物の息づかい
さらにジローラモさんは、鋳物職人の街・金屋町を歩きました。ここには「鐵瓶屋」や「金森銅器加工所」など、鋳物に関する工房が点在しています。なかでも音階のついた風鈴はとても珍しく、工芸の世界の奥深さを感じさせてくれました。見た目の美しさと音の響きを楽しむことができる逸品です。
老子製作所で見る鐘づくりの現場
旅の最終地点は「老子製作所」です。ここでは実際に鐘が作られている現場を見学することができました。鐘は「中子(なかご)」と呼ばれる中の型と「外型(そとがた)」を鋳物で作り、そこに合金を流し込んで完成させます。職人の元井さんは、鐘の形や響きにこだわり、ひとつひとつ丁寧に仕上げています。完成した鐘は、美しい音色とともに人々の暮らしに静かに寄り添っているのです。
ジローラモさんの旅は、ただの観光ではなく、その土地の人々の知恵や手仕事の価値をしっかりと感じる時間となっていました。自然と向き合いながら暮らす人々、そして代々受け継がれてきた文化や技術。富山の魅力は、そこに暮らす人々の想いと手間ひまの積み重ねによって守られていることが、旅を通じて伝わってきました。

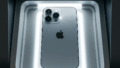
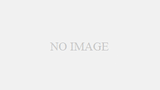
コメント