イマドキ自由研究がすごい!バナナの滑り実験からAI発明まで|2025年8月5日放送
「自由研究って、何をやったらいいのか分からない」「今どきの小学生はどんなテーマを選んでる?」そんな悩みを持つ親子にとって、ヒントが詰まったのが2025年8月5日放送のDayDay.特集。昭和や平成とは大きく変わった、令和の自由研究事情が紹介されました。バナナの皮で滑る実験や、AI・VTuberの活用、さらには病気のリハビリ器開発まで、発想もスケールも大人顔負け。この記事では、すべてのエピソードをわかりやすくまとめ、夏休みの宿題に悩む親子にも役立つ内容を紹介します。
1400組が参加!「自由研究フェスタ2025in東京」
番組冒頭では、東京都内で行われた体験型イベント「自由研究フェスタ2025in東京」の様子が紹介されました。会場には親子合わせて1400組が来場し、「植物標本づくり(新聞紙活用)」や「四角いしゃぼん玉作り」など、20を超える体験ブースが並びました。
中でも注目されたのが、ボール型のロボットをタブレットで動かすコーナー。最新テクノロジーと理科の融合は今や定番となり、パソコンやAIを使う自由研究も特別なものではなくなっていると伝えられました。
ChatGPTでテーマ探し?バナナの皮で実験する小学2年生
取材を受けた小学2年生のひなのさんは、「バナナの皮が本当に滑るのか?」を自由研究のテーマに選びました。きっかけは、母親がChatGPTに相談して出てきた20個の候補の中から選んだというもの。
実験方法は、床にバナナの皮を置き、その上にタオルを敷いてすべらせるという手法。実際に試してみると、皮の量が多いほど滑りやすくなることがわかり、結果をまとめてレポートに仕上げる予定とのこと。ゲーム感覚と科学の融合が、楽しく学べる研究に繋がっています。
VTuberアバター作成で自由研究!?6年生の本格的挑戦
小学6年生のあみさんは、自分で作ったキャラクター「アフロヒョウモンダコ」を使い、VTuberとして配信するまでの過程を自由研究にしました。
好きな猛毒生物「ヒョウモンダコ」をモチーフにデザインし、表情や目の動きまで細かく設定。リアルタイムで自分の動きに連動させるアバターづくりに10日間を費やしました。夏休み中には配信を行い、視聴者の反応や操作感をまとめてレポートにする予定です。配信技術やデジタル表現を活用した自由研究は、まさに時代を象徴するテーマです。
家族のために。平山病リハビリ機器を発明する小学5年生
さらに驚かされたのが、愛知県刈谷市の小学5年生佐々木大河くんの自由研究です。大河くんは母親が患う難病・平山病のリハビリを助けるために、機器を自作。
2年前に作った「パー力測定器DX」は、指の可動域や症状の変化を測るもので、特許庁長官賞を受賞。今年はさらに進化させ、ミラーセラピーを応用した「パー力回復機」を開発中です。
小指の動きの変化を数値やグラフで可視化し、医師の助言も取り入れて装置を調整。家族への思いが詰まった取り組みは、感動と実用性を兼ね備えたまさに社会的にも価値のある自由研究です。
自由研究=「面白い!」がカギ。食・脳・家族の疑問もテーマに
そのほかにも、個性豊かな自由研究が続々と紹介されました。
-
小6のさのさんは「お菓子を1ヶ月食べなかったら体に何が起こるか」を実験。結果、11日で2キロ減、肌荒れも改善という驚きの変化が見られたとのこと。
-
「どうしてきょうだいゲンカは起こるのか?」をテーマにした研究では、家族の会話や感情を分析してまとめた取り組みも紹介されました。
-
また、ピアノを弾く時にどのように脳が働いているかを調べる研究もあり、興味から始めて深掘りしていく姿勢が印象的でした。
今の自由研究は「知りたい」「面白そう」から始まり、自分なりのやり方で深めるのがスタンダード。そこにデジタル技術やデータ活用が加わることで、学びの形が広がっています。
【ソース】
・DayDay.(2025年8月5日放送/日本テレビ)
・自由研究フェスタ2025in東京
・北神経内科 ホームページ
・番組内紹介テーマ:ChatGPT/バナナ滑り実験/ヒョウモンダコVtuber/お菓子断ち/きょうだいゲンカ調査/脳活動観察

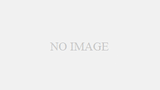

コメント