今季一番の冷え込みがもたらす“見えない危険”とは?若者もヒートショックに注意!
10月31日の朝、東京・渋谷からの中継では、街ゆく人々がコートに身を包み、白い息を吐く姿が見られました。東京都心の最低気温は9.7℃。今季初の一桁台となり、秋というよりも冬の気配を感じる朝です。
しかし、この寒暖差の中で注意しなければならないのは、ただの「冷え」ではありません。暖房器具の使い始めに起こる火災、そして体を襲う“ヒートショック”。どちらも命に関わる危険が潜んでいます。
暖房器具の“使い始め”が最も危険な理由
今月26日、新潟市で「ストーブが燃えている」と通報があり、消防車10台が出動。鎮火までに4時間を要しました。北海道・札幌市でも、ポータブルストーブが火元とみられる火災が発生。
製品評価技術基盤機構(NITE)によると、過去5年間で暖房器具による事故は596件発生し、うち約8割が「電気や石油暖房器具」に関係するもの。70人が命を落としています。
特に危険なのは“使い始め”。シーズン初点火の前に掃除を怠ると、ストーブの底に溜まったほこりが引火するケースがあります。久しぶりに使う際は、まず電源コードやプラグ、燃料タンク周辺に異常がないか確認し、ほこりを取り除いてから点火しましょう。
また、エアコンにも注意が必要です。内部洗浄の際に使用した洗浄液が電子部品に付着し、発火する事故も報告されています。エアコンを自分で掃除する場合は、内部に液体が入り込まないように注意し、可能なら専門業者に依頼するのが安心です。
電気カーペットも折りたたみ保管後の通電テストを怠ると、内部の配線が破損して発火する恐れがあります。折り目がついた状態で使用するのは厳禁です。
“ヒートショック”がもたらす突然の危機
寒暖差が激しくなるこの時期、家庭内での事故が増えるのが「ヒートショック」。急激な温度差によって血圧や脈拍が大きく変化し、失神や心筋梗塞、脳卒中などを引き起こす危険があります。
東京都内の銭湯神田湯では、2週間前から「ヒートショック注意」の張り紙を掲示。利用客の安全を守るために脱衣所や浴室の暖房を推奨しています。
いとう王子神谷内科外科クリニックの伊藤博道院長は「寒暖差10℃を超えるとヒートショックを起こしやすくなる」と説明。暖かい部屋から寒い脱衣所に移動して服を脱ぐと血管が収縮し、血圧が上昇。熱い湯に入ると今度は血管が拡張して血圧が急降下。その後、風呂上がりの冷気で再び急上昇。この短時間の血圧変動が脳や心臓に負担をかけ、失神や溺水事故につながるのです。
ヒートショックによる入浴中の死亡者は高齢者が中心で、厚生労働省の人口動態統計によると、入浴中の死亡の約8割が65歳以上。特に冬場に集中しています。
五輪金メダリストを襲った“脱衣所の罠”
1984年のロサンゼルス五輪で柔道金メダルを獲得した山下泰裕さんも、ヒートショックの恐ろしさを身をもって体験しました。
一昨年10月、家族で訪れた箱根の露天風呂で、湯船から上がろうとした瞬間に意識が遠のき、2メートルの崖下に転落。搬送後に頸髄損傷と診断されました。本人も取材に対し「ヒートショックのような状態だったのかもしれない」と振り返っています。
懸命なリハビリを経て、現在は回復し、来月から東海大学で柔道論の一部を担当予定。まさに奇跡の復活です。
若い世代にも広がる“寒暖差疲労”
ヒートショックは高齢者だけではありません。最近では、10代や20代の若者にも「寒暖差疲労」と呼ばれる症状が広がっています。
都内のクリニックには、10代の女性が頭痛や動悸を訴えて来院。数日間暖かい室内にこもっていたところ、寒い外に出て急に血圧が上昇し、帰宅後に急低下。血管の収縮と拡張を繰り返したことで自律神経が乱れ、体調不良を引き起こしたと考えられています。
伊藤院長は「寒さに慣れていない体は、ちょっとした温度差でも強いストレスを受ける」と指摘しています。
日常でできる“ヒートショック予防策”
・脱衣所や浴室をあらかじめ暖めておく
・お湯の温度は41℃以下に設定し、長湯を避ける
・入浴前にはかけ湯をして体を慣らす
・食後・飲酒後すぐの入浴は控える
・サウナ後の水風呂は一気に入らず、少しずつ体にかける
さらに、「寒冷順化」と呼ばれる予防も有効です。寒さを避けずに軽く外出し、ウォーキングやストレッチで体を寒さに慣らすことで、血圧変動を抑えることができます。特に下半身の筋肉を動かすことで、血流を保つ“足のポンプ機能”を鍛えることができるため、冷えに強い体づくりに役立ちます。
命を守るための“冬支度”
・ストーブや電気カーペットは使う前に清掃・点検
・脱衣所と浴室の温度差を10℃以内に保つ
・入浴中は無理せず、家族がいるときに入る
・若者も「寒暖差疲労」に要注意
寒さは一見ただの季節の変化ですが、その裏には命を脅かす危険が潜んでいます。今季一番の冷え込みを迎える今こそ、家庭の中にあるリスクを見直すチャンスです。暖房のほこりを落とす、脱衣所を温める、体を寒さに慣らす――その一つひとつの行動が、冬を安全に過ごすための備えになります。

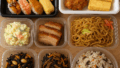

コメント