腸から元気になる!“今買うべき腸活食材”とは?
最近なんだか疲れやすい、風邪をひきやすい…そんな悩みを抱えていませんか?それ、腸の乱れが原因かもしれません。11月7日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス!』では、医師と管理栄養士が「今こそ買うべき腸活食材」をテーマに、健康のカギを握る8つの食材を紹介しました。舞台はMEGAドン・キホーテ大森山王店。インフルエンザが流行する季節にぴったりの“免疫力を底上げする買い物術”が明かされました。この記事では、番組で登場した全レシピと専門家のおすすめを分かりやすくまとめます。
【DayDay.】夏の便秘は“腸の砂漠化”が原因?医師が教える暑さ対策&腸活術|2025年8月7日
腸活の基本3ステップ「入れる・育てる・出す」
番組の冒頭で、医師がまず伝えたのは腸活の三原則。
-
発酵食品で「菌を入れる」
-
食物繊維で「菌を育てる」
-
排泄で「老廃物を出す」
この3つのサイクルを意識することで、腸内の善玉菌が活発に働き、免疫力の底上げにつながるというのです。体調を崩しやすい冬こそ、腸内環境を整えることが風邪やインフルエンザ予防の第一歩になると強調していました。
発酵食品の王様!“キムチ×もち麦”で菌を育てる
最初に紹介されたのは、定番の発酵食品キムチ。植物性乳酸菌が豊富で、腸内の善玉菌を増やす働きがあります。特に注目すべきは、商品パッケージにある“キムチくんマーク”。これは日本漬物協同組合連合会が定めた「乳酸菌で熟成発酵されたキムチ」の証です。加熱処理で乳酸菌が死んでいるものもあるため、このマーク付き商品を選ぶのが大切だと紹介されました。
さらに、キムチと相性抜群なのがもち麦。水溶性と不溶性の食物繊維をバランスよく含み、腸内の乳酸菌を“育てるエサ”になります。番組では、医師の麻生先生が紹介した炊き込みご飯が話題に。
●料理名:キムチとサバのもち麦炊き込みご飯
材料(2〜3人分)
・米 1合
・もち麦 50g
・サバ水煮缶 1缶(汁ごと使用)
・白菜キムチ 60g
作り方
-
炊飯器に米ともち麦を入れ、通常の水加減でセット。
-
サバ缶(汁ごと)とキムチを加え、通常通り炊飯。
-
炊き上がったら全体をよく混ぜて完成。
POINT
もち麦の豊富な食物繊維が腸内フローラを整え、キムチの乳酸菌が善玉菌を増やします。さらにサバに含まれるビタミンDが免疫力アップをサポート。おかずいらずで満足感のある“腸活主食”です。
納豆と切り干し大根のW発酵コンビ
続いて紹介されたのは、納豆。発酵食品の代表格であり、納豆菌が腸内の悪玉菌を減らしてくれます。管理栄養士の麻生さんが勧めるのは、ひきわり納豆と切り干し大根のサラダ。切り干し大根の食物繊維が納豆菌をサポートし、腸の働きを活発にします。
●料理名:納豆&切り干し大根サラダ
材料(作りやすい量)
・切り干し大根 30g
・納豆 1パック
・大葉 4枚
・麺つゆ(3倍濃縮) 大さじ1
・すりごま 大さじ1
作り方
-
切り干し大根を水で戻し、しっかり水気を絞る。
-
納豆、大葉、すりごまを加え、麺つゆで和える。
POINT
ひきわり納豆の細かい粒が大根と絡みやすく、シャキシャキ食感が楽しい一品。食物繊維+納豆菌+発酵のトリプル効果で、朝のスッキリを助けてくれます。
腸が喜ぶ“なめ茸とチーズのパスタ”
続いての注目食材はナチュラルチーズ。加熱殺菌をしていないため、乳酸菌が生きたまま腸に届きます。特におすすめは粉チーズ。サラダやパスタなど、どんな料理にも手軽に使える万能食材です。
番組では、なめ茸と粉チーズを使った腸活パスタを紹介。なめ茸はきのこの中でも食物繊維が豊富で、善玉菌のエサになる成分がたっぷり。組み合わせることで、乳酸菌と食物繊維の相乗効果が期待できます。
●料理名:なめ茸とチーズのパスタ
材料(1人前)
・パスタ 100g
・なめ茸 適量
・粉チーズ 適量
作り方
-
茹で上がったパスタになめ茸を混ぜる。
-
仕上げに粉チーズをたっぷりとかけるだけ。
POINT
火を使わず簡単にできるのに、腸にうれしい“菌の共演”。チーズのうまみとなめ茸のとろみで、満足感の高い一皿になります。
医師が常備している“ヨーグルトとキャベツ”の最強コンビ
発酵食品の定番ヨーグルトももちろん登場。選ぶときのポイントは、乳酸菌とビフィズス菌の両方が入っているもの。それぞれ働きが違うため、ダブルで摂取するのが理想です。さらに、きなこ+はちみつをトッピングすると、腸活の“黄金トリオ”になります。
麻生先生が自宅で常備しているというのがこちら。
●料理名:キャベツとヨーグルトのコールスロー
材料(作りやすい量)
・千切りキャベツ 300g
・塩 少々
・プレーンヨーグルト 大さじ5
・マヨネーズ 大さじ2
・酢 大さじ2
作り方
-
キャベツと塩を袋に入れてもみ、水分を出す。
-
ヨーグルト・マヨネーズ・酢を加え、さらにもみ込む。
-
冷蔵庫で5分以上置いて完成。
POINT
3日間保存可能。発酵と食物繊維のW効果で腸をやさしく整えます。冷蔵庫に常備しておけば、朝食やお弁当の付け合わせにもぴったりです。
専門家が選ぶ!今すぐ買うべき“腸活アイテム”
店内を巡る中で紹介された注目アイテムも見逃せません。
・ぬか漬け:植物性乳酸菌が豊富。ぬか床にはビタミンB群やミネラルも含まれ、免疫バランスを整える効果が期待されます。
・らっきょう:ごぼうの約3.5倍の食物繊維。腸内の善玉菌を増やし、便通を促進。
・あずきのチカラ おなか用(桐灰化学):レンジで温めて使う温熱グッズ。おなかを温めて血流を促進し、便秘解消をサポート。
・ピュアココア:甘くないタイプを選ぶのがポイント。豆乳や黒糖、はちみつと組み合わせるとより効果的。
・ポップコーン:レタス1〜2個分の食物繊維を含み、意外にも腸活スナックとしておすすめ。
さらに医師は、腸の動きを助ける腹筋運動やバランスボールも勧めていました。腸腰筋を鍛えることで“出す力”をサポートし、腸内のリズムが整うそうです。
まとめ:毎日の食卓で“腸が喜ぶ”習慣を
この記事のポイントを整理すると――
・キムチ、納豆、チーズ、ヨーグルトなどの発酵食品で「菌を入れる」
・もち麦、切り干し大根、キャベツで「菌を育てる」
・運動や温活で「腸を動かす」
腸を整えることは、体と心の健康を守る第一歩。今日の食卓から一品、“腸が喜ぶメニュー”を取り入れてみましょう。毎日の積み重ねが、免疫力を底上げし、寒い冬を元気に乗り切る力になります。
出典:日本テレビ『ヒルナンデス!』(2025年11月7日放送)


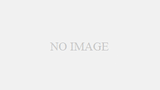
コメント