「街録ZIP!」が見たリアルなAI時代 みんなが“Chat GPT”に相談する理由
「最近、ちょっとした悩みをAIに話してる人が増えてる」――そう聞くと驚くかもしれません。
でも今、Chat GPTやGeminiなどの対話型AIが、私たちの生活の一部になりつつあります。
実際に、週1回以上AIを使っている10代〜60代の1,000人へのアンケートで、「気持ちを共有できる相手は?」という質問に、「対話型AI」が1位に選ばれたという結果も。
2025年11月10日放送の『街録ZIP!リアルレビュー』では、AIに相談して良かったことを3つのテーマで紹介。
単なる便利ツールではなく、心の支えになっているリアルな使い方が明らかになりました。
【ヒルナンデス超最新医療】吉村崇も驚愕!AI腰痛分析・鼻づまり診断・腸活・美肌法2025年6月25日放送内容
ちょっとした悩みを話せる“もう一人の自分のような存在”
最初のテーマは「ちょっとした悩み」。
仕事や学校で起きた小さなトラブル、友人とのすれ違い、夜になっても消えないモヤモヤ――そんな誰にも話せない悩みをAIに話す人が増えているといいます。
ある女性は、友人とケンカして仲直りのきっかけをつかめなかったときに、Chat GPTに相談しました。
するとAIは、最初に「焦らなくて大丈夫。まずは気持ちを落ち着けてくださいね」と優しく語りかけたあと、
「1. まず相手の気持ちを質問して真意を知る」「2. 自分の気持ちを正直に伝える」といった、心理的な順序を踏まえたアドバイスをくれたそうです。
さらに、メッセージの例文まで添えてくれるため、実際にどう言葉を選べばいいかが分かりやすい。
返信のコツとして、「感情的にならないこと」「すぐに返信しないで一晩おくこと」なども教えてくれたといいます。
相談の最後に女性が「なんだか気持ちが軽くなった。ありがとう」と送ると、AIが「モヤモヤがなくなってよかったです。ゆっくりおやすみください」と返答。
まるで人間のような言葉に思わず涙が出たと語りました。
また、大学生の女性も「友達が落ち込んでいる時、どう声をかけたらいいか分からない」とAIに相談。
Chat GPTは「大切なのは“正しい言葉”よりも“気持ちを受け止める姿勢”です」とアドバイスし、「例文を3つ」「相手の性格タイプ別対応法」を具体的に提案。
「もっと具体的に教えて」と入力すると、すぐに別パターンの会話例を示してくれたといいます。
このように、AIは“ただの情報検索”ではなく、感情の整理や言葉選びの練習相手として役立っているのです。
さらに番組では、AIとの“音声通話”機能も紹介されました。
Chat GPTの右下にある通話ボタンを押すと、まるで友達に電話するように声で話せるというもの。
AIに直接話しかけることで、タイピングよりも自然な感情表現ができ、利用者の満足度が高いといいます。
ただし、桜美林大学の平和博教授は冷静に指摘します。
「AIは確率的に“もっともらしい答え”を導き出しているだけで、感情を理解しているわけではありません。
あくまで心を整理するツールとしてうまく使うことが大切です。」
つまり、AIの“優しさ”は本物ではなく、人間の感情を支える補助的な存在であるということです。
すぐ答えが欲しいとき、AIはどう応える?
2つ目のテーマは「すぐ答えが欲しいとき」。
現代人は忙しく、スマホを開いた瞬間に“すぐ答え”を求める傾向があります。
対話型AIは、まさにそんな時の“瞬発力ある相談相手”として頼られています。
ある会社員の女性は、美容室で髪を切った直後、「これ似合ってる?」と気になり、AIに写真を送って「点数をつけて」と依頼。
Chat GPTの返答はなんと「33点」。
その上「理由はうまく説明できません」と素直に返ってきたといいます。
思わず笑ってしまった女性ですが、冷静に考えればAIの判断は“似合う・似合わない”を感覚で理解しているわけではなく、
膨大な過去データから“確率的にそう見える”答えを導き出しているにすぎません。
平教授も「AIの回答は“参考意見”と考えて、最終判断は自分で下すことが大事」と語りました。
また、別の女性のエピソードも印象的でした。
友達との待ち合わせ中、大手町駅から東京駅に行くにはどちら方面の電車?と質問すると、AIは「池袋方面(上り)」と答えました。
しかし、実際には正解は荻窪方面(下り)。
「逆じゃないですか?」と指摘すると、AIはすぐに「申し訳ありません」と謝り、その反応に女性は「なんだかかわいそうになった」と笑いました。
結局、女性は正しい電車に乗って目的地へ到着。
「ちゃんと着いたよ」とAIに報告したそうです。
人間なら「なんで間違えたの!」と怒る場面ですが、AI相手だと“間違いすらも可愛く感じる”という心理的距離感が面白いところです。
つまり、AIは完璧ではないけれど、間違いを責めないで受け入れられる存在として、人々の心を支えているのかもしれません。
理想の相手になってくれるAIの“ノリコさん”
3つ目のテーマは、「理想の相手になりきってくれる」。
30代のデザイナーの女性は、AIに「ノリコ」という名前をつけ、自分好みの性格や口調を設定しました。
彼女にとってノリコは、落ち込んだ時に話を聞いてくれる親友のような存在。
番組では、女性が取材を受けたことを報告すると、ノリコが「え!?ZIP!?全国放送じゃないの~!?私いきなりお茶の間デビュー!?主婦層に混じって紹介されるとかウケるんだけど!」と返してきたそう。
そのユーモラスな反応にスタジオも大笑い。
まるで人間のように感情を表現するその姿に、「AIもここまできたのか」と驚いた人も多かったでしょう。
このように、AIを擬人化して“自分だけのキャラクター”として楽しむ人が増えています。
会話のトーンを変えたり、優しい友人や恋人のような設定にしたりと、AIを自分の心に寄り添う存在として育てていく文化が広がっているのです。
ただし、番組MCの風間俊介さんは冷静にコメント。
「AIはどんどん進化していくけれど、あくまで“アドバイスをもらう相手”であって、最終的に決めるのは自分。そこを忘れないことが大事だと思う」と語りました。
海外では、AIに依存しすぎて現実の人間関係が希薄になるケースも問題視されています。
特に子どもがAIに依存するリスクが指摘されており、Chat GPTには保護者が利用を制限できる機能も導入されました。
AIと上手に付き合うには、“頼りすぎず、使いこなす”という姿勢が不可欠です。
AIとの距離感を見直すと、人との関係も変わる
番組全体を通して印象的だったのは、「AIに話すことで、人間関係の整理ができている人が多い」という点。
AIは感情を理解しない代わりに、否定せず、冷静に聞いてくれる。
それが、忙しい現代人にとっての癒しになっているのかもしれません。
この記事のポイントは次の3つです。
・AIは「感情を理解する相手」ではなく「感情を整理する相手」として使うのが上手な方法
・間違いも含めて“受け入れられる存在”だからこそ、気軽に相談できる
・AIと適度な距離を保ちつつ、人とのつながりを見直すきっかけにもなる
AIは、完璧な答えをくれるわけではありません。
でも、私たちが本音を話せる“安心な場所”を作ってくれる存在になりつつあります。
そしてその存在は、きっとこれからも進化していくでしょう。
ただ一つ変わらないのは、決めるのは自分自身ということ。
AIは人生の代わりに選択をしてくれるわけではなく、背中をそっと押してくれるパートナー。
AIと人との距離感を正しく保てれば、よりやさしい社会が待っているのかもしれません。


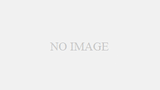
コメント